2025年10月18日(土)宮崎大学錦本町ひなたキャンパス(宮崎市錦本町)にて宮崎大学日本語教育シンポジウムを開催し、約70名の皆様にご参加いただきました。
近年、DeepLなどの翻訳AI(人工知能)やChatGPTなどの対話型生成AIは、日本語教育の現場においても注目を集めています。一方で、「AIに仕事を奪われるのではないか」「最新の技術についていけるのだろうか」といった不安の声も聞かれます。また、文部科学省が策定した「日本語教育の参照枠」は、欧州評議会が策定したCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を参照して推進されていますが、宮崎県内の教育関係者においてCEFRの理解は十分に浸透していません。
本シンポジウムでは、このような背景を踏まえ、宮崎大学で日本語教育を担当している4名(小柴裕子・椎葉淑乃・和田恵・狩野貴美子)が「宮崎大学におけるChatGPTを取り入れた日本語授業実践 ~初級から上級までの課題と展望~」と題して、2024年度から新たに行っているChatGPTを活用した授業におけるメリット・デメリットなどを紹介した後、琉球大学の葦原恭子氏、京都大学の大木充氏、マカオ大学の李羽喆氏、早稲田大学の李在鎬氏に講演していただきました。
全ての講演を通して、日本語教育とAIの関わりにおける可能性や課題について考える有意義な場となりました。宮崎大学では、各高等教育機関や自治体、地域企業、国際協力機関と幅広く連携しながら、地域の国際化や多文化共生社会の実現に積極的に貢献していきます。


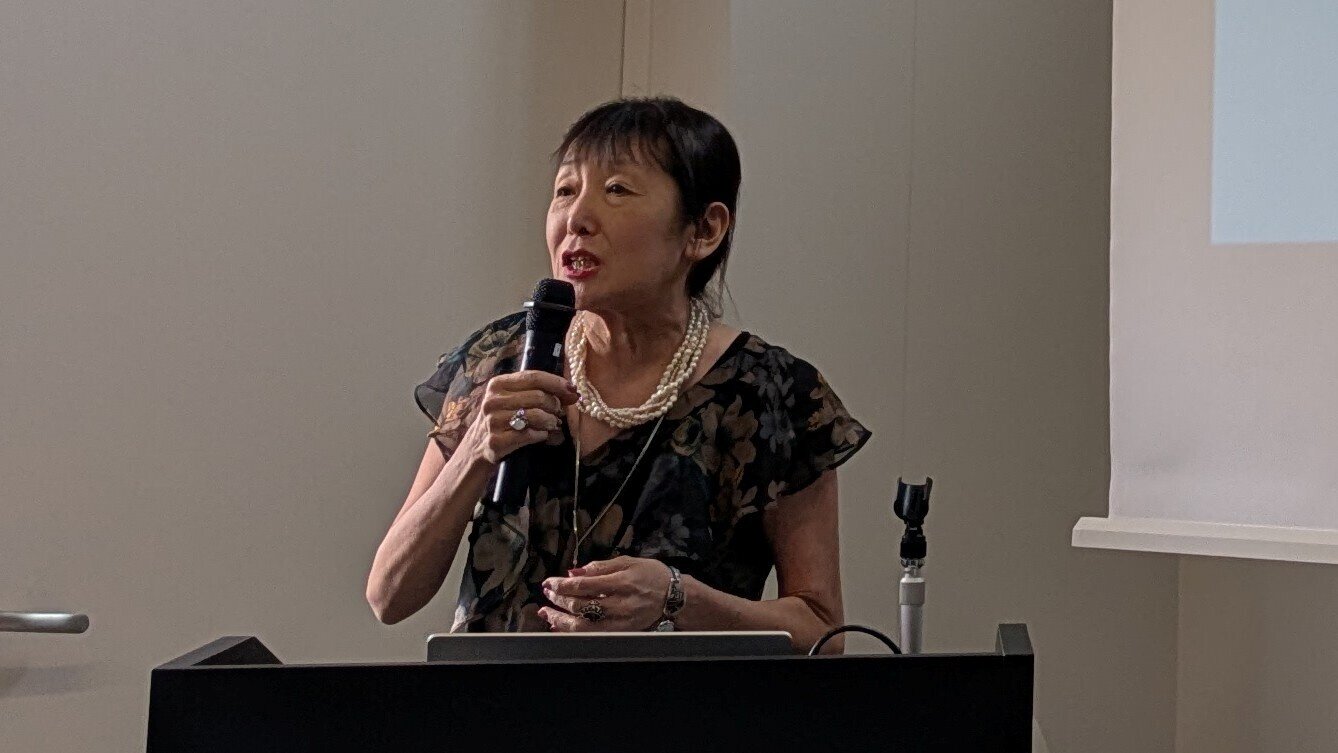
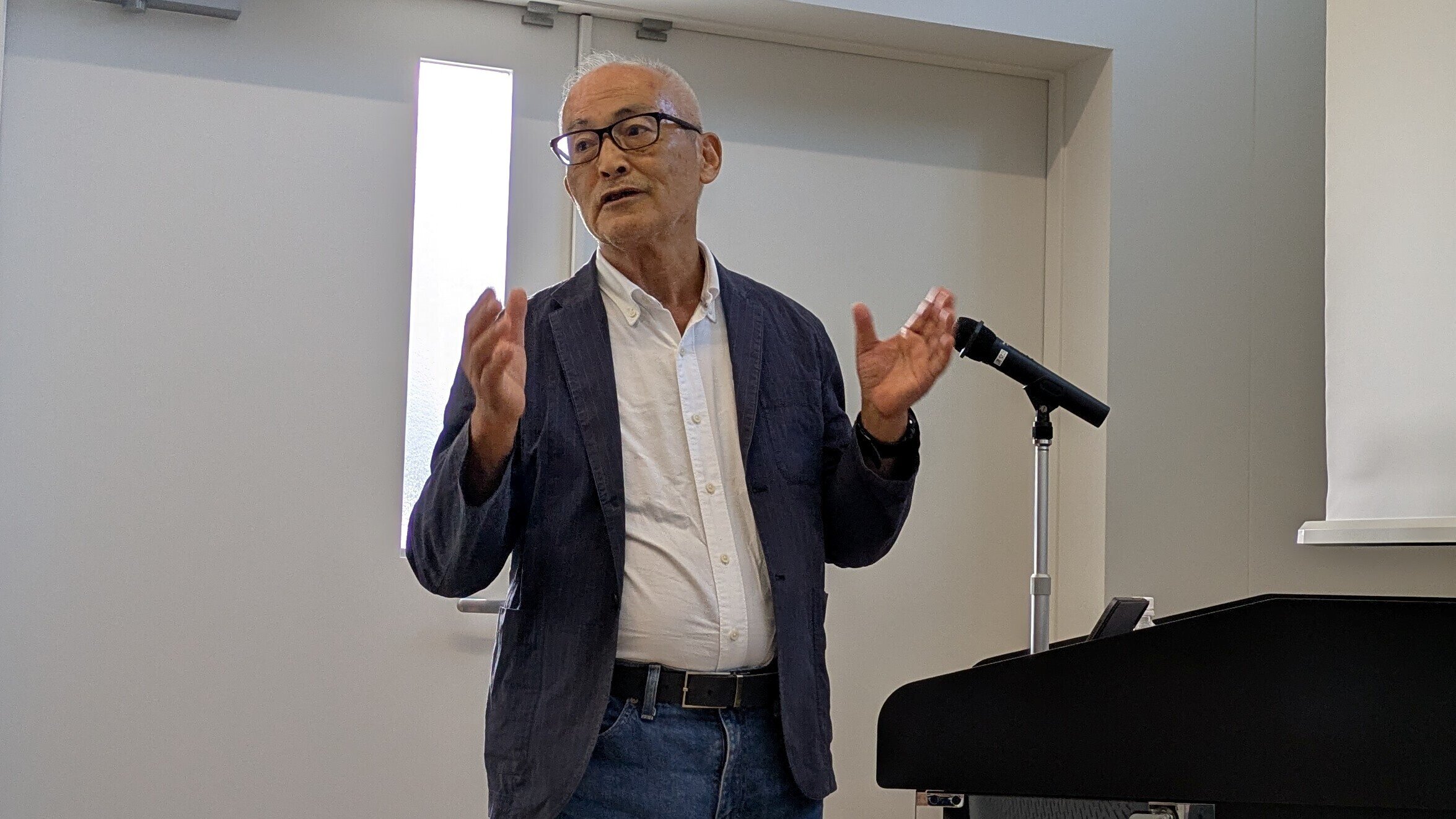



今回の演題と講演者は以下のとおり。
※ このシンポジウムは、科学研究費助成事業 李在鎬「生成 AI を組み込んだ日本語作文診断システムの開発と普及に関する研究」(24K00078 研究代表李在鎬)、葦原恭子「日本語教育人材に求められる異文化間コミュニケーション能力とは -Cando の構築 -」(23K00610 研究代表葦原恭子)、大木充「翻訳 AI・生成 AI による自律性支援と学習者の動機づけ」(24K04053 研究代表大木充)、李羽喆「Opportunities and Challenges in Japanese LanguageEducation in the Greater Bay Area: GenAI and Language Policy Perspectives」(SRG2024-00059-FAH 研究代表者李羽喆 ) の一環として行われました。