2017.12.11 掲載
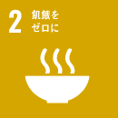





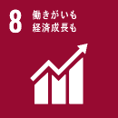


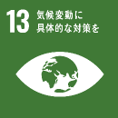
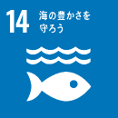


いま思い返せば、学生時代に座学ばかり重要視して、実習の授業は手を抜いていたせいで、知識と技術が結びついておらず、"活きた知識・技術"として構築できていなかったのです。指導書ばかり読んでいても野球はうまくならないことと同じです。また、そんな技術は自分の将来には必要ないものと勝手に判断して切り捨てていたのかもしれません。今でこそ分かるのですが、農学関係者である以上、卒論や卒業後の進路において基本的な栽培技術は求められることが多いです。在学中にしっかり構築していれば、その時に自信をもって円滑に研究や仕事を進めることができると思います。
そのことが身に染みて分かった私は、知識と技術を結びつける場である学生実習において二つの改善を図りました。
まず一つ目は、空白の期間を減らすこと。従来の実習では、例えばトマトであれば、定植の実習から一か月後に整枝等の管理実習、更に一か月後に収穫の実習を行って終了、という感じでした。これでは学生は断片的にしかトマトを目にすることができず、空白の期間が生まれてしまいます。日々成長する植物の管理方法を学ぶにあたって、この期間にこそ断片的な知識・技術を体系的に繋ぎ、活きた知識・技術を構築する大きな役割が含まれています。これを非常に勿体ないと思った私は、学生一人一人に区画を設定し(写真2)、担当区画内の植物は定植から整枝誘引・着果処理・収穫などの栽培管理を一貫して行ってもらう事にしました。これで学生がいつでも自由にハウスに来て観察・管理することが可能となり、向上心のある学生ほどより多くの技術を習得できるようになりました。また、学生毎の習熟度の差も担当した区画の植物体の様子や収量から判断できるので、私も個々に合わせた指導を行えるようになりました。これは木花フィールドが大学構内に設置されているので可能な事であり、その利点を十分活用していることにもなります。実習のできる農場が農学部の建物から歩いて数分のところにあるなんて、理想的な大学農場だと思いませんか?
二つ目は、実習を行うハウスにおいて、農学部の各先生方の研究成果などを積極的に取り入れ、常に最新の技術を導入すること。つまり授業で習う知識を、実用的な技術として体感して学べるということです(写真3)。ハウスで果菜類を取り扱う実習なので、現状では天敵や環境制御が中心ですが、できるだけ多くの先生方の研究成果を組み込めないかといつも考えています。宮崎大学には各専門の優秀な先生方が揃っていますので、その英知を結集して他大学に負けない充実した実習環境を学生の皆さんに提供することが私の目標の一つです。
余談ですが、平成29年に施設園芸の最先端国であるオランダの農業を現地視察する機会を頂きました(写真4および5)。トマトを80t/10a(日本は15tぐらい)収穫するオランダの栽培技術ですが、植物生理に基づいて光合成速度が最大となるようなハウス内の環境値を決定・制御し、、、~云々。ここではとても書ききれないので今回は省略しますが、いつかは木花フィールドのハウスでも実現して実習教育に活かし、世界的にも最先端の技術を学生の皆さんに伝えていくことができたらと構想を練っています。
今回は施設野菜の紹介しかできませんでしたが、木花フィールドでは他に水田や果樹、畑作、露地野菜なども扱っており、それぞれ有意義な実習を行っています。さらにGAP認証も取得しており、そのような実習環境を有する大学農場があるのは、宮崎大学だけです。大学選びには授業内容だけでなく実習の充実度も大切です。これを読んだ方に、宮崎大学農学部の実習教育に対する熱意が少しでも伝わってくれれば、と願っています(写真6)。
※JGAP/ASIAGAPが取り組む「農場の持続性に向けた7つの取り組み」のうち、
本記事の活動は「農場管理」「食品安全」「環境保全」「人権の尊重」「労働安全」が対象。
▽SDGsとGAPの関わりはこちら▽
一般財団法人 日本GAP協会「JGAP/ASIAGAPの7つの取り組み」
https://jgap.jp/uploads/media/9YUIODAVAA