【イベントレポート】附属中学校PTA実践活動 × アマテラスガールズプロジェクト連携企画
理系への“まなざし”を育てる一日──宮崎大学でのアマテラスガールズ連携企画が開催されました。
2025年7月5日(土)、宮崎大学木花キャンパスにて、「附属中学校PTA実践活動 × アマテラスガールズプロジェクト連携企画」が開催されました。
対象は宮崎大学附属中学校の2年生(全4クラス、115名)と保護者の皆さま。中学生が大学の学びに触れ、将来の進路選択に向けた視野を広げることを目的に、講演会と体験講座をローテーション形式で実施しました。
大学で過ごす、“学びの日”
初めて足を踏み入れるキャンパスに、生徒たちは少し緊張した様子でしたが、スタッフの案内で徐々に和やかな雰囲気に。4クラスの生徒を2班に分け、講演と体験講座を交互に体験する形式でプログラムを行いました。
講演レポート|「理科は“わからない”を確かめる学び」
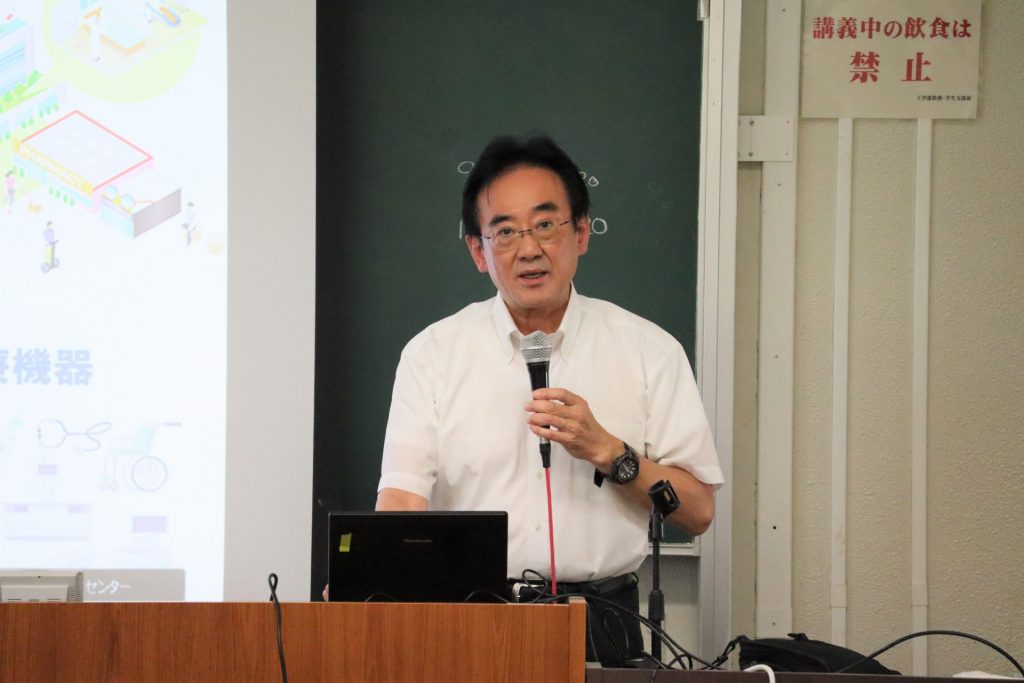
本企画の冒頭では、宮崎大学工学部長・鈴木祥広先生よりご挨拶をいただきました。
鈴木先生は、「電気・水道・通信といったライフラインや、道路・橋・医療・暮らしを支えるあらゆる仕組みは、すべて工学の力によって成り立っている」と語り、工学の意義と社会への貢献の広さについて紹介されました。
また、工学は50年後・100年後の未来にも必要とされる分野でありながら、現在の中高生には、まだ十分に知られていない部分が多いことにも触れ、「工学の魅力や価値を正しく伝えることが今後ますます重要になる」と工学の魅力やポテンシャルについてご説明いただきました。
続いて、宮崎大学工学部の特色ある教育体制についても説明がありました。
入学後に進路を柔軟に変更できるカリキュラム、高校物理未履修でも基礎から学べる授業、融合的な学びを促す全分野共通の基礎教育、そして情報・データ・AI分野における文部科学省認定プログラムなど、丁寧で手厚い教育環境が整っていることが紹介されました。
研究面でも、多様で先進的な研究が展開されており、「カーボンニュートラル」「医工連携」「環境・防災」といった社会的テーマにおいても、世界と競える研究レベルにあると述べられました。
「宮崎大学工学部は、教職員全体で学生を丁寧に支え、成長を引き出す体制を整えている」との言葉は、生徒・保護者にとって、大学の学びを“自分ごと”として考えるきっかけになったようでした。

吉野賢二先生 講演〜わからない”を確かめることから、理科は始まる〜


講演を担当されたのは、宮崎大学工学部 電気電子工学プログラム 教授・吉野賢二先生(研究室サイトはこちら)。
この日は中学生に向けて、学びの本質、そして大学の役割について、ストレートな言葉で語ってくださいました。
講演は、「理科って何のために学ぶの?」という問いかけから始まりました。
先生は、理科が「暗記する教科」だと捉えられがちな現状に触れながら、「理科は、“本当にそうなのか”と確かめる学び。覚えるより、考えることが大事」だと説明。
また、仮説・実験・検証という科学的なアプローチの流れを、中学校→高校→大学の探究のステップとともに紹介。
中学では「疑問を持つこと」、高校では「科学的に考えること」、大学では「答えのない問いに向き合うこと」と、学びの深まりを示しながら、「大学は、“問いを持ち続ける場所”である」と語りました。
さらに、「失敗を重ねる中にこそ、本当の学びがある」と、理科の授業や実験を“作業”にしないでほしいというメッセージも。
生徒たちには、「自分なりに試して、自分なりに確かめる姿勢が大切」と繰り返し伝えられました。
講演の終盤、生徒たちの表情は少しずつほぐれ、メモを取りながら耳を傾ける姿が印象的でした。
「理科=覚える教科」から、「理科=自ら確かめる教科」へ。
吉野先生のことばは、理系の世界がぐっと身近に感じられるきっかけとなったようでした。
講演後の質疑応答では、生徒から「たくさんある研究テーマの中から、どのように決めるのですか?」という質問が出されました。
吉野先生は、
「急には決められない。日頃から、研究に限らずいろんなことに疑問を持ち、イメージを持って生活することが大切です。すると、あるとき“ピン”とくることがあるんです」
と答えられました。
さらに「これから進路を考える上で大切なことは?」という質問も。
吉野先生からは「30〜40歳くらいの自分をイメージしてみてください。理想像を描いて、その理想に向かって努力すれば、自然と道が見えてきます。遠回りしても大丈夫。目標が明確なら、きっと道は開けます」
また、吉野先生のその他の質問の際には、大学院で求められる力についても話がありました。
「研究の世界では、何よりも“実績”が重視されます。やるべきことに向かって結果を出すことは大前提です。もちろん、頑張る姿勢も大切ですが、“成果”はそれ以上に問われます」
という厳しくも現実的なメッセージに、生徒たちも静かに耳を傾けていました。
ラズベリーパイ体験講座「自ら動かすことで見えてくる世界」


もう一方のプログラムは、宮崎大学工学部技術センター協力によるラズベリーパイを使った体験講座。
「ラズベリーパイ」とは、教育用に開発された小型コンピュータで、パソコン操作やプログラミングを気軽に学べる機材です。
生徒たちは2人1組で、モニターやキーボードを操作しながら、基本的なコード入力やLEDの点灯などを体験しました。
最初は戸惑っていた生徒も、画面上に変化が現れると一気に集中モードに。
「わあ、光った!」「もっと光る秒数を長くしてみよう!」といった声が教室に広がり、講座後には「プログラミングって苦手だと思っていたけど意外と楽しいかも」という感想も寄せられました。
難しさを感じた場面でも、ペアの相手と相談したり、学生スタッフに質問したりしながら、あきらめずに取り組む姿が印象的でした。
普段は触れる機会の少ないテクノロジーを動かす側を体験することで、生徒たちの中に新しい興味や好奇心の芽が芽吹いているようでした。
保護者と大学がつながる機会に


講演・体験中、保護者の方々にもお子さんの活動を見守っていただきました。
大学という空間に足を踏み入れ、「わが子が大学でどんなことを学ぶのか」「自分たちの頃とはどう違うのか」と、保護者にとっても新鮮な体験になったようです。
「真剣に向き合う姿がみられた」「宮崎大学のことを知るいい機会となりました」という声も聞かれ、子どもだけでなく保護者にとっても有意義な時間となりました。
教育の現場と大学が手を携えて
この企画は、附属中学校PTAとアマテラスガールズプロジェクトの連携により実現したものです。
関係者の丁寧な連携により、大学・学校・保護者が同じ方向を向いて生徒の学びを支える、連携の形が実現しました。
さいごに
“理系に進むかどうか”は、人生の大きな選択のひとつかもしれません。
けれど、それ以前に、「世界の見え方がちょっと変わった」「“なぜ?”と立ち止まるのが楽しくなった」――そんな気づきが、未来の選択を支えてくれるはずです。
宮崎大学工学部「集まれ!宮崎アマテラスガールズプロジェクト」は、これからも子どもたちの“まなざし”を育む場づくりを、学校・保護者・地域と共に進めてまいります。
