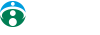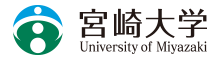学部・学科又は課程ごと、研究科又は専攻ごとの目的
- トップページ
- 宮崎大学運営について
- 公開情報
- 法定公開情報
- 学校教育法施行規則等に規定する情報
- 大学の教育研究上の目的に関すること
- 学部・学科又は課程ごと、研究科又は専攻ごとの目的
学部・学科・課程
教育学部
教育学部は、宮崎県教育委員会等との連携により、地域密接型を目指す宮崎大学の主要な学部として、義務教育諸学校に関する地域の教員養成機能の中心的役割を担うとともに、宮崎県における教育研究や社会貢献活動等を通じて我が国の教育の発展・向上に寄与することを基本理念としています。この基本理念に基づき、以下の教育目的を掲げております。
- 1.教員養成の観点から要求される専門的知識、専門的学力を身につけること
- 2.様々な知識や技能を総合して、現代的課題を的確に判断し、解決する力を養うこと
- 3.幅広い教養を身につけた豊かな人間性と道徳性、及び積極的意欲をもった主体性を育成すること
- 4.国際感覚をもつとともに、地域の自然や文化や歴史を理解し、国際社会及び地域社会の発展に貢献しうる能力を育成すること
医学部
医学部は、昭和49年国の無医大県解消施策・一県一医大構想のもとに設立された宮崎医科大学を前身とし、平成15年10月の統合により、その29年の歴史を終え宮崎大学医学部となりまた。本学部の使命は「地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に、進歩した 医学・看護学を修得せしめ、人命尊重を第一義とし、医の倫理に徹した人格高潔な医師、医学者、 看護職者及び看護学研究者を育成し、国内外の医学及び看護学の水準向上と社会福祉に貢献すること」を使命としています。
医学科
宮崎の地域医療に貢献でき、国際的にも活躍できる優れた医師及び医学研究者の育成を目指しています。本学科の卒業生は、医師として、医学研究者として、あるいは医学教育者として幅広い分野で活躍し、医学の発展と社会福祉の向上に貢献しています。
看護学科
宮崎大学医学部看護学科は昭和49年に設立された宮崎医科大学が前身であり、平成13年に併設されました。平成15年10月年に旧宮崎大学と統合して、宮崎大学医学部看護学科として、現在まで多くの優秀な医療人・医学研究者を世に送り出しています。わたくしたちは、日頃から統合後の新生宮崎大学のスローガンである『世界を視野に地域から始めよう』のもと、地域社会はもとより広く世界に通用する医療人、医学研究者の育成を目指しています。看護学科の卒業生は、人間性豊かな看護師、保健師、または助産師として人々の健康への援助を実践し、看護学の発展ならびに社会福祉に貢献しています。
工学部
工学部は、宮崎県唯一の工学系学部として、”宮崎に根ざし世界に目を向けた工学部”を目標に、今後ますます進展する高度な科学技術に挑戦し、創造することができる人材の育成につとめ、国際的にも評価される質の高い学術研究活動を進めています。さらに、地域産業の発展を推進することにより、地域社会に知的な貢献をすることにつとめています。本学部では、2012年度の大幅な改組改編により、環境ロボティクス学科と工学基礎教育センター、環境・エネルギー工学研究センター、国際教育センターの新設や学科構成の見直しなどを行いました。【環境応用化学科】・【社会環境システム工学科】・【環境ロボティクス学科】・【機械設計システム工学科】・【電子物理工学科】・【電気システム工学科】・【情報システム工学科】 の7学科の連携協力による教育・研究分野の高度化、学際化、総合化を推し進め、21世紀の地球環境と共生できる科学技術の創造と、それを担う人間性豊かな人材の育成を目指しています。
環境応用化学科
化学における基本原理の探求から先端技術開発にわたる学術研究を通じて、人類が解決しなければならない課題に対す る化学の役割と使命を果たすために環境応用化学を設置します。これによって、地球環境や生態系を保全する物質・資源・エネルギーの製造及び循環プロセスに 関する知・技の創造と継承を図り、それに関わる人材育成を目指しています。
社会環境システム工学科
社会環境システム工学科では、自然との共生を図りつつ生活・経済・文化・安全を支える社会基盤の充実に貢献できる高度技術者の育成を目指しています。
環境ロボティクス学科
本学科のコンセプトは、人々の生活や労働環境をより良いものにするロボット機器などを開発する知識を教育し、近未来の生活環境を創生することにあります。ハ イブリッドカーなど、最近の工業製品の開発には機械、電気・情報、化学工学など融合的な知識が必要になっていています。そこで、環境ロボティクス学科は. 融合分野に強い人材、具体的には、「機械を設計し、これに電子回路およびコンピュータを組み込み、さらに環境を考慮したシステムを開発する知識をもつこと で、近未来の生活環境を創生する人材」を育成することを目的としています。また、本学科で学ぶことで、ロボットや福祉機器など人々の生活や労働を支える自 動化機器を開発する知識が身につきます。
機械設計システム工学科
現在までの日本の「ものづくり」の技術は、日本の産業を 支えてきましたし、21世紀のこれからの産業界においても中心的な役割を担っていきます。その「ものづくり」の基幹となる学問の一つが機械工学です。機械 工学は、私達の頭の中にあるアイデアを、具体的に形ある機械へと作り上げていく学問分野と言えます。機械設計システム工学科では、「人と自然にやさしいも のづくり」を基本理念に掲げ、機械と自然との調和を考え、人間の生活をより豊かにする機械を創造できる高い倫理観を備えた機械技術者の育成を目指しています。
電子物理工学科
現在、産業の発展を支える新しい電子材料開発技術およびエネルギー関連技術などの広い科学技術に寄与 できる有能な人材が求められています。特に太陽電池関連産業および電子産業分野などの高度技術社会に対応できる人材を育成します。電子物理工学科では、科 学技術者として高い倫理性を兼ね備えた人材育成を行い、専門職業人としての課題解決能力の習得が出来るような教育体制を作っています。
電気システム工学科
現在、安全で安心な低炭素・高度情報化社会を実現する基幹技術として電気エネルギー工学と通信システム工学が融合した新しい産業技術の創出と人材育成が期待 されています。電気システム工学科では、電気エネルギー技術や情報通信技術を中心に現代社会を支える基盤技術の基本原理と基礎知識を習得させ、社会の変化 や要請に対応できる電気システム工学分野の専門技術者の育成を行います。
情報システム工学科
情報システム工学科では、社 会からの人材育成並びに21世紀の情報通信社会を支える人材育成の需要を考え、情報科学の理論、計算機の構成や基本ソフト、情報解析技術などの基礎情報科 学分野と、情報ネットワーク、生産情報システムなどの産業情報システム分野の双方で幅広く活躍できる人材の育成を目指しています。
農学部
農学部は、食料、環境、資源及び生命に関する基礎知識の理解をもとに、広い視野で物事を考える総合的判断力や問題解決能力を涵養しつつ、社会の要請に応え るための農学に関する高度な専門性と技術を修得させ、それらに関する問題解決を通じて地域と国際社会に貢献できる人材を育成することを理念とする。
植物生産環境科学科
植物生産環境科学科では、安全・安心な農産物の安定的・持続的供給を行うための農学全般について学びます。また、自然循環機能や天敵を利用した環境保全型農業、環境調和型雑草防除、植物工場、農業の機械化や労働環境の改善、農地整備や灌漑利水、農業経営・経済などに関する専門科目についても実験・実習を交えながら学びます。
森林緑地環境科学科
森林緑地環境科学科では、森林・農山村・都市域を、相互に作用し合う一つの連続した空間として捉えます。人間活動と自然をつなぐ複合的な新しい学際領域です。その連続した空間における自然環境の保全と安全で快適な生活環境の形成、および生物資源の高度な利活用を視野にいれ、森林緑地の恩恵(機能)の解明とそれに基づく技術の確立を目指して教育・研究を行います。
応用生物科学科
「生命・食料・環境問題を解決するために生物や食品に潜む機能をいかに活用するか」というテーマを中心に課題探求型の教育研究システムを用意しています。1、2年次では教養教育と並行して生物学や化学などの専門基礎科目を徹底して学習します。専門教育では生命・食料・環境を網羅する各分野の専門講義および実験を履修します。本学科は、生物工学や食品関連分野における幅広い知識と先端技術の習得を目標に教育を行います。
海洋生物環境学科
海洋は地球の環境を和らげ、生物資源に満ちています。このような水圏環境について深く学び、生物の多様性と利活用を理解・修得することによって、広く人類の未 来について思索し、地域ばかりなく、国際社会に通用する教育・研究を行うことを目的としています。
畜産草地科学科
低コスト・低労力化のもとで、限られた自給飼料の リサイクルに基盤をおいた畜産に関する基礎的、応 用的な知識を身につけるばかりでなく、食料や飼料 自給率の向上、自然・社会環境の調和を目指しながら、 国内外の「食料・農業・農村」をめぐる諸課題 の解決にも貢献できる人材を育成します。
獣医学科
獣医学は動物の疾病の予防・診断・治療のための学問として発達してきましたが、生活の多様化や高度化に伴い、研究分野は動物の保健の向上のみならず、公衆衛生、医薬品開発、動物愛護、環境保全など、広範囲にわたる生命科学の重要な一翼を担っています。獣医学科は広範な分野で高度な専門性を発揮できる獣医師、さらに動物医学を基本とした幅広い応用能力を身につけ、高い実践能力を備えた人材の育成を目指しています。
畜産別科
畜産別科は、地域社会における指導者的立場となりうる農業後継者の育成を目標としています。
地域資源創成学部
地域資源創成学部では、マネジメントの専門知識と社会・人文科学、及び農学・工学分野の利活用技術の基礎知識を教授する異分野融合のカリキュラムを構築するとともに、研究 者教員と実務家教員とが協働した実践的教育、宮崎県全域をフィールドとした実習や国内・海外インターンシップによる地域の方々と一体となった協働教育を導入します。このような教育により、地域の製造業、食品・醸造業、マスコミ、観光、サービス業、国・自治体、経済団体の幹部候補や、事業承継者、起業家などに必要な知識・技能を教授します。人材像としては、持続可能な地域づくりを包括的にマネジメントでき、地域資源を理解し利活用しつつ、ビジネス・地域産業、行政などの現場で、革新的な価値を創出できる人材の輩出を目指します。その上で、地域資源創成学部のOB・OGを核として地域の産学官の人的ネットワークを形成し、地域の持続的発展に末永く貢献していくことを究極の目標とします。
企業マネジメントコース
国内外の産業経済構造を俯瞰的に捉え、地域の社会経済状況を調査・分析し、その知見をもって、国内市場や海外市場の開拓やリンケージ構築、企業誘致、起業等、地域経済の発展に向け、既存の産業に新たな価値創造(イノベーション)を引き起こし、地域の産業振興に寄与する次世代のビジネスリーダーを養成します。
地域産業創出コース
地域資源(農業・自然・文化等)の価値を理解し、地域資源を活用した新商品の企画、ビジネスの新展開、様々な切り口からの地域資源の魅力発信等を通じて地域資源に新たな価値を見出し、6次産業化や観光等の地域の産業創出につなげることができる人材を養成します。
地域創造コース
中山間地域における過疎・高齢化、中心市街地衰退等の課題解決や、地域社会の維持発展に向けて、地域における住民の組織やネットワーク、行政制度等について理解するとともに、地方都市・農山村の経済機能、社会機能、環境機能を総合的に捉え、地域活動を有機的に連結し、活性化できる持続可能な地域づくりをトータルマネジメントできる人材を養成します 。
大学院・専攻・コース
教育学研究科
本学大学院教育学研究科は、学部における専門教育又は教職経験の基礎の上に、確かな教育観と幅広い視野を持ち、高度の専門知識、研究力及び実践力を備えて、学校教育をはじめ教育の諸分野において教育研究の中核となり、併せて地域文化の向上に寄与しうる人材の養成を目的としています。
学校教育支援専攻
臨床心理学、教育心理学、障害児教育学、日本語教育学の各分野についての理論的研究を深め、その研究成果に立って、各分野の理論の確立と研究の方法論並びに実践力の修得を目指します。
教職実践開発専攻
教職実践開発専攻は、専門職学位課程の教職大学院であり、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、小学校、中学校及び中等教育学校等の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成のための教育を行うことを目的としています。
看護学研究科
医科学看護学研究科は、平成15年に医科学専攻、そして平成17年に看護学専攻が設置され、平成22年4月、大学院改組により医学系研究科から医科学看護学研究科に名称変更しました。本研究科は「人間の複雑多彩な生命現象を形態学的、生理学的並びに生化学的に研究し、自然環境、社会環境をも研究対象として社会に貢献できる高い研究能力を持つ研究者を育成すること」を使命としています。
研究者育成コース
「研究者育成」コースは、看護学の教育者・研究者としての基礎づくりをするコースであり、学士教育を基 盤として、人間の個体としての特性や看護学の体系化、教育評価、看護技術の開発や実践効果の検証などを積極的に推進していく能力を育成する教育者・研究者 の育成を目的としています。
実践看護者育成コース
「実践看護者育成コース」は、専門看護師の育成を行う「がん看護領 域」、実践力を有する助産師を育成する「実践助産学領域」(免許取得課程)と、実務経験のある助産師のキャリアアップを図る「実践助産学開発領域」を設置 し、教育・臨床で研究的思考を持って実践する看護専門職の育成を目的としています。
工学研究科
平成28年度に従来の6専攻を改組し、新たに工学専攻(1専攻3コース)を設置しました。工学専攻では、隣接する研究分野を融合させてコース化するとともに、1専攻化して専門分野の垣根を取り払い、学士教育の単なる延長ではない融合型専攻として、分野別の垣根を越えた教育プログラムを構築することにより、幅広い視野、専門応用能力、コミュニケーション能力、国際性を育成します。さらに、育成した能力をもとに専門性を深化させることによって、工学分野の高度専門知識を修得して応用でき、自ら課題を探求し、その解決に向けて高度専門知識を活用し主体的に考え、研究開発を通じて必要となる日本語、英語によるコミュニケーション能力を有する、産業界等で国際的に活躍できる実践的な応用力を有する高度専門技術者を育成します。
環境系コース
本コースは、化学系・社会環境系の融合コースであり、自然と共生し、環境と調和した機能物質や物質生産プロセスを創生できる高度専門技術者、ならびに自然と共生した社会基盤・生産基盤の充実や環境保全に貢献できる高度専門技術者の育成を目指します。環境汚染防止、環境修復やエネルギーと資源の有効利用などの環境問題解決のための化学技術、ならびに社会資本整備、地域防災や環境保全等の地域社会の問題解決のための技術や政策の提供などの社会的ニーズに基づき、科学技術の持続的発展に貢献できる創造性豊かな人材を養成します。
エネルギー系コース
本コースは、電気電子系、電子材料系、応用物理系の融合コースであり、国際的な視野で広くエネルギーに関わる科学技術を通じて社会の持続的発展に貢献できる創造性豊かな高度専門技術者の育成を目指します。エネルギー技術は高度情報化された社会インフラを支えるキーテクノロジーの一つであり、エネルギーの低炭素化やエネルギーシステムのスマート化など高度利用技術開発の促進などの社会的ニーズに基づき、電機、自動車、半導体等の製造業、情報・通信関連産業にとどまらず、さまざまな産業界等で技術者・研究者として活躍する人材を養成します。
機械・情報系コース
本コースは、機械系・ロボティクス系・情報系の融合コースであり、豊かで質の高い暮らしと持続可能な社会を実現するため、人間の生活支援と資源や環境を考慮したものづくり技術を支える設計加工分野、計測制御分野及び情報技術分野の高度専門技術者の育成を目指します。工業製品の多機能化と知能化、生活支援・環境制御における先進技術の創造、高度情報化社会の実現などの社会的ニーズに基づき、科学技術の持続的発展に貢献できる創造性豊かな人材を養成します。
農学研究科
農学部・農学研究科の母体である宮崎高等農林学校は、中等教育からの更なる教育の向上を指向して、大正13年に設置されました。新制国立大学の発足時には、宮崎農林専門学校(昭和19年宮崎高等農林学校から改称)は、宮崎大学農学部として承継されました。昭和42年、大学教育の基礎の上に高度の専門的な知識と技能を修めるとともにわが国農業の近代化に即応するため、高級技術者、研究者並びに教育者の養成を目的に農学研究科修士課程が設置されました。
植物生産環境科学コース
植物生産環境科学コースでは、植物機能の開発・向上、生物環境の解析・制御、生産・加工・流通における農業生産環境の改善、地域生態系の管理等に関する高 度な専門知識を備え、併せて、国際的視野を持ち、安全で持続的な植物生産とその利活用に寄与できる人材の育成を目指します。植物生産システムについての高度な専門的知識と農業課題に対して科学的考察ができ、経済活動と環境に調和した生物資源の適正な管理・利用、食料生産における機械化・装置化など農業生産環境の向上・発展を担う人材を養成します。
森林緑地環境科学コース
森林緑地環境科学コースでは、森林及び緑地の環境保全と生態系修復、森林資源や水資源の持続的利用に関する先端技術を備え、国際社会での活躍も視野に、資源・環境問題に指導的な立場で活躍できる高度専門技術者・研究者の育成を目指します。森林・緑地の機能に関する高度な専門知識と技術を広く修得し、それらを応用して諸課題に意欲的に取り組み、自らの判断プロセスを論理的かつ効果的に他者に伝えるための高度なプレゼンテーション能力および豊かなコミュニケーション能力をもつ人材を養成します。
応用生物科学コース
応用生物科学コースでは、生物科学に関わる知識と技術を有し、応用生物科学分野での科学技術の発展に寄与できる知識と実践力を備え、国際化・情報化時代に対応できる高度技術者および研究者の育成を目指します。生物機能や食品機能に関する高度な専門知識と技術を有し、理論的な理解力と応用生物科学分野の先端的・独創的な科学技術を応用し、地域・国際的に寄与でき、目的達成のための計画をデザインし、調査研究を進め、情報を正確に解析して発信できる語学力とプレゼンテーション能力をもつ人材を養成します。
海洋生物環境科学コース
海洋生物環境科学コースでは、海洋・河川・池沼など水圏における生物生産につながる幅広い基礎知識と応用技術を備え、水圏生物の生物多様性および生態系との調和を前提とした生産・利用技術の発展に貢献できる高度専門技術者及び研究者を育成します。水圏環境の保全、増養殖、魚病対策、未利用資源の開発等に関する研究結果を論理的に説明するためのプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力をもつ人材を養成するとともに、当該分野の中心的リーダーとして国際的に活躍できる人材育成を行っています。
畜産草地科学コース
畜産草地科学コースでは、「土-草-家畜のつながり」と「from Farm to Table」の教育理念に基づき、環境調和型・持続生産型の安全で高品質な畜産物生産システムに関する高度な教育研究を通じて、国際的視野を持ち、畜産草 地に関して多面的に展開できる理論と専門的技術を修得した高度な専門職業人の養成を目指します。環境調和型・持続生産型の安全で高品質な畜産物生 産システムに関する高度な専門的知識や技術を備え、自然環境と調和のとれた持続的なシステムの構築に伴う諸課題を多面的観点から論述し、解決策を提示でき る能力、地域・国際社会の「食料・農業・農村」をめぐる諸課題に、協調・倫理性を持ちながら自らの考えを提示・表現できる人材を養成します。
農学国際コース
農学国際コースでは、農学専攻(一専攻)の特色を活かし、国際的に、特にASEAN諸国で重要視されている問題点に対応して、分野横断型課題探求・問題解決型の3つの実践プログラムを提供します。また、海外の学術交流協定校と連携した相互交流教育を実践することにより、農学に関する多様で高度な専門知識・技能を国際的に活用し展開できる高度専門技術者及び研究者の育成を目指しています。
医学獣医学総合研究科
本研究科は、国内では初めて医学と獣医学が連携・融合して設置された大学院です。これまでの医学と獣医学それぞれで培われてきた教育・研究実績を踏まえて、それらを連携・融合することにより、今までは得られなかった両分野における知識、研究能力を身につけることができます。また、グローバル時代の課題である食料問題や新興・再興感染症対策を始めとする医学・獣医学にまたがる諸課題を解決できる人材を養成することも目的としています。このような教育・研究を通して、本研究科が立地する畜産基地からの要請に応えるとともに、人類の健康と福祉の向上に貢献します。
医科学獣医科学専攻(修士課程)
本専攻の使命は、生命科学の発展と社会の福祉の向上に寄与することです。各コースでは、以下を備えた人材を育成します。また、博士課程とも協働して、医学と獣医学が連携・融合した総合的な教育研究を行い、地域の要請に応えるとともに地球規模での問題解決に貢献できる人材養成を目指します。
- 「生命科学研究者育成コース」では、医学と獣医学が連携・融合することにより、生命科学に関する広範な知識に基づいた総合的判断力と研究能力を備え、技術・知識基盤社会の形成に資する研究者及び教育者の養成を目的とします。このコースでは、生命科学に関する広範な知識を学んだ上で、医学ないし獣医学研究における重要な基盤技術を修得し、自立した研究者として研究を行うための基礎を修得することができます。
- 「高度医療関連技師養成コース」では、高度な研究マインドに裏打ちされた質の高い医療関連技師の養成を目的とします。このコースでは、医療現場における専門的医療支援技能者が、合理的・科学的な思考能力やより高度な専門知識と技術を修得することができます。
- 「生命倫理コーディネーターコース」では、希少性のある専門職業人として今後の社会ニーズが期待される臨床倫理コンサルタントの養成を目的とします。このコースでは、生命科学や医療における倫理コンサルトに関する基礎知識と専門的スキルを修得することができます。
医学獣医学専攻(博士課程)
本専攻の使命は、医学・獣医学の発展と社会の福祉の向上に寄与することです。各コースでは、以下を備えた人材を育成します。
- 「高度臨床医育成コース」では、高度の専門性が必要とされる医療業務に必要な診断・治療技術と高い倫理観に裏打ちされた専門性、医学、獣医学、その他の生物学的研究に関する幅広い基礎知識とそれに裏打ちされた医療情勢の変化に対応する能力、動物実験などの臨床研究遂行に必要な知識と経験や人獣共通感染症に関する幅広い知識等に裏打ちされた研究能力を有する高度専門職業人としての臨床医を育成します。
- 「高度獣医師育成コース」では、伴侶動物や産業動物の健康を管理するために必要な高度な診断技術と治療法及び研究能力を身につけた獣医師および指導的獣医師、また、食肉衛生、家畜衛生及び公衆衛生関係で働く獣医師に対して指導できる高度獣医師を育成します。
- 「研究者育成コース」では、医学、獣医学及び他の生物学的研究に関する幅広い基礎知識、様々な基礎研究の遂行に必要な動物実験等の知識と実験手技、自立した研究者として様々な情勢の変化に対応しながら研究を進める能力を有し、医学、獣医学及び両分野に関連した研究領域で国際的に活躍できる研究者を育成します。
農学工学総合研究科
農学工学総合研究科は、自然科学の分野において、専門的かつ学際的な研究・教育を行い、科学・技術の発展に資するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた人材を養成することを目的とする。
資源環境科学専攻(博士後期課程)
- 1.環境共生科学
- 2.持続生産科学
資源環境科学専攻では、資源の枯渇、自然及び生活環境の悪化、食料危機などの人類が直面しつつある課題に取り組むために、資源の有効利用と資源循環による環境負荷の低減を基調とした、安全で活力ある循環型社会の構築に貢献できる高度専門技術者の養成を目的とする。
生物機能応用科学専攻(博士後期課程)
- 3.生命機能化学
- 4.水域生物科学
生物機能応用科学専攻では、動植物、微生物及び水産生物資源が有する諸機能の解明と、それに基づいた知見により、本地域及び国際社会が抱える食料・エネルギー・環境問題に貢献できる高度専門技術者の養成を目的とする。
物質・情報工学専攻(博士後期課程)
- 5.新材料エネルギー工学
- 6.生産工学
- 7.数理情報工学
物質・情報工学専攻では、環境調和・循環型及び高度情報化社会の課題に取り組むために、環境調和型新材料の構築、エネルギーの変換・解析、省エネルギー化・高度情報化された生産技術の開発、高度なアルゴリズムとソフトウェアを活用した情報処理技術及び数理モデルの構築に貢献できる高度専門技術者の養成を目的とする。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
- トップページ
- 宮崎大学運営について
- 公開情報
- 法定公開情報
- 学校教育法施行規則等に規定する情報
- 大学の教育研究上の目的に関すること
- 学部・学科又は課程ごと、研究科又は専攻ごとの目的