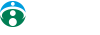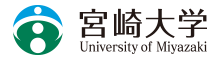明日死ぬつもりで今日がんばる ~ 国内最高峰レースMt.FUJI100で総合22位に輝いたトレイルランナー教授 ~板谷 智也(いたたに ともや)さん
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- 明日死ぬつもりで今日がんばる ~ 国内最高峰レースMt.FUJI100で総合22位に輝いたトレイルランナー教授 ~板谷 智也(いたたに ともや)さん

板谷 智也(いたたに ともや)さん
医学部看護学科 生活・基盤看護科学講座 教授
1975年生まれ。
石川県輪島市出身。長男として生まれる。弟1人
小学校5年生の頃にサッカーを始め、中学校まで続ける。
輪島高等学校ではボクシング部に入部。フェザー級(57kg)の選手として県大会優勝を果たす。
1998年 福井県立大学(看護短大部)入学
2001年 東京都内の病院で看護師として勤務
2006年 語学留学(アメリカニューヨーク)
2007年 新潟県のスキー場でスノーボードインストラクターとして勤務
2009年 大阪大学医学部保健学科に3年次編入学。在宅現場での仕事もしながら、保健師の資格取得を目指す
2011年 大阪大学大学院修士課程
2013年 大阪大学大学院博士課程、東京で保健師として勤務
2015年 金沢大学医薬保健研究域保健学系助教、博士号取得
2023年 宮崎大学医学部看護学科教授(現在に至る)
専門分野:在宅看護
資格:看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
好きな言葉:明日死ぬつもりで今日がんばる
尊敬する人:鏑木毅さん(プロトレイルランナー)
好きな食べ物:チョコレート
38歳の頃(2013年)から本格的に登山を始める
40歳の時(2015年)、トレイルランニング(トレラン)に挑戦
44歳の時(2019年)、日本百名山を全頂制覇(最後は屋久島宮之浦岳)
2017年から本格的にトレイルランニング(トレラン)を始め、これまでに完走した100km以上のトレイルランレースは10大会。
トレイルランニング(トレラン)の主な実績 ※【 】内は距離と累積標高(m+)
2019年 Ultra-Trail Mt. Fuji - UTMF 【160km】 ※天候不良によりレース途中で大会中止
(2020-2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で主要大会は中止)
2022年 ウルトラオリエンテーリング・諏訪大社-善光寺【102km コントロール:30 カ所】
総合2位(61人中)、タイム:11時間38分25秒
2022年 Ultra-Trail Mt. Fuji - UTMF【165km】
総合49位(1470人中)
2022年 UTMB®(ウルトラトレイル・デュ・モンブラン) 【172 km / 10180 m+】
総合521位 (1788人中)、タイム:36時間34分35秒
2023年 Yarikan100 - 72K 【71 km / 3630 m+】
総合6位(167人中)、タイム:10時間43分00秒
2023年 比叡山 International Trail Run - 50km 【48 km / 3310 m+】
総合12位(760人中)、タイム:6時間59分04秒
2023年 中能登トレジャートレイルラン- 50mile 【76 km / 2860 m+】
総合2位(30人中)、タイム:8時間11分49秒
2023年 Ultra-Trail Mt. Fuji【164km】
総合32位(2,386人中)、タイム:25時間09分
2024年 MtFUJI100【162 km / 7348 m+】
総合22位(2,145人中)、タイム:24時間29分55秒
■ 人生色々 ~紆余曲折を経て40歳を前に博士号を取得~
私は福井県の学校で看護師免許を取得しました。正直に言いますと、看護師を目指した明確な目標はありません。強いていうなら「生物学が好きだった」くらいでしょうか。福井県で看護師免許を取得したのち、新宿区にある東京女子医大病院(通称「女子医」)に就職にしました。都内の大学病院を選んだのも「都会の大きな病院で働きたい」という理由でした。女子医での勤務は大変ではありましたが、東京で、看護師として充実した生活を送っていたと思います。ただ、なんとなく惰性で人生を送っているような気がして、5年で女子医を退職しました。
--- その後、アメリカに語学留学したそうですが? ---
退職時には人生に対する漠然とした焦燥感はありました。しかし、何か明確な目標があったわけではありません。とにかく「何かを変えなきゃ!」と思っていたように思います。そして、とりあえず留学をすることにしました。特別な理由はなく、強いて言うなら「海外生活への憧れ」といったところです。ちなみにこの時、ニューヨークの語学学校にしましたが、これも単なるニューヨークという町への憧れだけで決めました。この時はまだ「人生の目標」的なものが見つかっていませんでした。
--- アメリカ留学から帰国後はスノーボードで全日本選手権を目指す ---
アメリカから帰国後、しばらくはアルバイト生活でした。看護師をすることもあれば、飲食店や建設現場で働いていたこともあります。色々な人に関わりながら人生の方向性を模索していました。そんなある日、知り合いのスノーボードインストラクターから「新潟のスクールで働かないか?」という誘いを受けました。実は看護師になった頃からスノーボードを始めており、冬には毎週のように新潟のゲレンデに通っていました。スノーボードスクールで指導を受け、努力を重ねて2級の技能検定にも合格しました。連絡をくれたのは、そのスクールでお世話になったインストラクターでした。
それから冬の間は新潟のスクールで働き、夏は東京で仕事をする生活が始まりました。スクールでの仕事は大変なこともありましたが、とても楽しかったです。毎日練習を積み、どうしたら良いインストラクターになれるか日々考え続けていました。この期間は私の人生にとって特別なものでした。スクールには多くのスノーボード選手が在籍しており、その影響で私も選手登録をして大会を転戦していました。結果は思うように出ませんでしたが、4年目には雪山生活を終えることを決意しました。当時お付き合いしていた今の妻と結婚を考えていたからです。インストラクターの収入で生活を続けるのは難しいと感じたため、最後の1年は全てを賭けて頑張ろうと決意しました。

△スノーボードインストラクター時代(スノーボードスクールにて)※左から2番目が板谷さん
--- 看護師から保健師に軌道修正、そして編入生向け模試で全国1位に ---
毎日厳しいトレーニングに励みました。早朝から働き、仕事を終えてジムでトレーニングを積んだあと、室内ゲレンデに行って練習をし、夜遅くに帰宅する生活でした。シーズンインしてからも、早朝からゲレンデのナイターが消えるまで練習をしていました。私の目標は全日本選手権への出場でした。私はその年の関東ブロックの予選に出場しました。しかし、あと一歩で敗退し、夢は絶たれました。ただ、この一年が私の人生を変えました。目標をもって生活する素晴らしさを知ったからです。
雪山生活を終えて普通の生活?に戻ることを考えた時に、病院の看護師は考えませんでした。別のことがやりたいと思ったのです。当時の政府は「健康寿命の延伸」を政策として掲げていました。予防医学が重要になると考えた私は保健師を目指すことにしました。保健師養成校への入学を目指すにあたり、私は予備校に通うことにしました。もともとは専門学校に入学するつもりでしたが、予備校の講師から勧めがあり大学編入を目指すことにしました。受験勉強とスノーボード、全く違うように思えますが、「目標達成」という観点からすると同じでした。私はスノーボード選手として活動した経験を活かして勉強しました。短期間で急激に成績は伸びました。編入生向けの模擬試験があるのですが、全国模試で1位にもなりました。そして看護の編入では最難関の大阪大学に合格することができました。
■二度とトレランの大会には出ない!
40歳の時です。トレイルランニングをしていた友人の吉川賢一さんに誘われ、「北丹沢12時間山岳耐久レース(神奈川県相模原市)」に参加することになりました。通称「北丹」と呼ばれるこのレースは、距離にして45km、累積標高(登り距離)は約3000メートルです。私は38歳の頃から本格的に登山をしていましたから、「この程度であれば何とかなるかな」と甘い考えで参加してみたのです。しかし、それが大間違いでした。まともに走れたのは最初の15kmくらいでした。そこから先は脚が痛くなり、ちょっと走ってはすぐ歩く状態で、泣きそうになりながら進みました。全ての関門を制限時間ギリギリで突破し、何とか完走しました。実はこの時、大雨の影響でコースが37kmに短縮されました。これがなければゴールはできていなかったと思います。とにかく厳しいレースで、「二度とトレランの大会には出ない!」と思いました。
それから、特にトレイルランニングの練習をしていたわけではありませんでしたが、1年後に再び同じ大会に参加しました。たまたま近所のアウトレットでトレランシューズを見つけたからです。実は前年、知識ゼロの私はスニーカーで北丹を走っていました。お店で手に取ったトレランシューズは、山道でも滑らないような加工が施されていました。「これを履いたらもっと快適に走れるのでは?」と思いました。結果としては、天候に恵まれたこともあり、前回よりもはるかに快適なランができました。順位は最後尾に近かったですが、それでも制限時間にはかなり余裕をもってゴールできました。これに味をしめた私は、地元石川県で開催される「峨山道(がさんどう)トレイルラン」に出走しました。距離は74キロです。この時はシューズだけでなく、リュックやウェア、食料など完璧な装備でレースに臨みました。過酷なレースでした。ゴール後は震えが止まらなくなり、血尿がでました。体を酷使したのだと思います。ただ、結果は驚きの順位でした。出走約300人中の55位でした。私は上位に位置するこの結果に大喜びし、トレランにはまっていったのです。

△峨山道(がさんどう)トレイルランにて
■友人が語ったとんでもない目標がいつのまにか自分の目標に
峨山道のしばらくあとの出来事です。私をトレランの世界に誘った吉川賢一さんが、私にとんでもない目標を話してきました。彼は「UTMBを目指しているんだ」と言いました。UTMB(Ultra-Trail-Du-Mont Blanc)はフランスのシャモニーという町を拠点に開催される大会です。ヨーロッパアルプスの最高峰、モンブランを中心とした山岳地帯をフランス、イタリア、スイスの三か国をまたぎ一周します。世界最高峰と称されるUTMBはすべてのトレイルランナーが憧れるレースです。しかし、その過酷さは半端ではありません。UTMBは総距離171キロメートル、累積標高は10,000メートルに及びます。最も高いところで標高2,500メートルにもなる山岳地帯を一昼夜走り続けます。74キロの峨山道でボロボロになった私には想像ができない世界でした。「ありえない」そう思いました。
調べれば調べるほどUTMBの過酷さを知りました。しかし、なぜだかUTMBへの興味が膨らむばかりでした。気が付けばUTMBの出場要件を調べていました。当時の出場要件は、ITRA(国際トレイルランニング協会)の認定するレースに出場し、レースごとに付与されるポイントを直近3レースで15ポイント獲得していることが条件でした。このポイントはレースの距離と累積標高によって設定されるのですが、概ね100キロのレースで5ポイント、それ以上だと6ポイントになります。私はITRAが認定する国内のレースを調べました。私が出走可能で、かつ6ポイントが付与されるレースが二つ見つかりました。どちらも当然ながら過酷なレースでした。でも、「もしこの二つをゴールできたら、UTMBの要件を満たせる」と思いました。正直なところ、当時の走力ではこの二つのレースを完走するのは難しい状況でした。しかし、「やってみてだめなら仕方ない。挑戦しない方が後悔する」と思いました。そして、この二つのレースの完走に向けて本格的にトレーニングを開始したのです。
2017年11月に完走した峨山道はITRAから3ポイントが付与されていました。2018年9月は「上州武尊スカイビュートレイル」に参加しました。距離は130キロ、累積標高が約7,000メートルです。初めて夜を超えるレースでしたが、何とか完走し6ポイントを獲得しました。その翌月の10月には「OSJ KOUMI100」に出走しました。このレースは距離が165キロ、累積標高は約7,000メートルです。とにかく過酷なことで有名なこのレース、完走できるか否か、ぎりぎりのチャレンジでした。朝の5時にスタートし、レースが終わったのは翌日の午後3時過ぎ、およそ35時間、意識が飛びそうになりながらゴールしました。まさに地獄のレースでした。このレースでも6ポイントを獲得し、合計15ポイント、ついにUTMBの出場要件を満たすことができました。

(2019年に開催されたUTMBスタート時の様子、milestone社様より提供)
※写真引用:https://milestone81.com/
■UTMBの参加資格は満たしたが・・・
トレイルランニングを初めてから、わずか2年余りでUTMBの参加資格を満たし、トントン拍子でUTMBにも出場して完走するつもりでいました。しかし、ここからが長い道のりでした。UTMBは世界中のトレイルランナー達にとって憧れの舞台であり、まさに世界最高峰の大会です。参加資格を満たしたランナーが多数申し込むため、参加できるかどうかは抽選で決まります。
応募を終えた私は「このまま抽選にも当たるのでは?」と軽い気持ちで結果を待っていました。ここで当たれば2019年の出走権を獲得できます。しかし、送られてきた通知は「Negative draw」、外れてしまいました。そして、残念ながら翌年も落選し2020年の出走権を逃しました。しかし、当時のルールでは2年連続して落選したランナーは3年目に優先出走権が与えられるため、2021年大会は出走できるはずでした。
ところが、2021年と言えば、新型コロナウイルス感染症が流行している状況です。世界的に厳しい入国規制が行われていました。どこの国でも、他国から入国した場合に2週間程度の隔離機関が設けられていました。実質的には海外のレースに出場できる状況にはありませんでした。一方で、ヨーロッパでは日本ほどは厳しい規制がなく、大会自体は開催されました。私はこの年のUTMBに出ることができないのですが、出走権は消費されてしまうと思っていました。失意のどん底でした。
しばらくしたのち、UTMBからありがたい通知が届きました。「新型コロナの流行を鑑み、出走権を翌年に持ち越せる」という知らせです。私は権利を持ち越し、ついに2022年大会の出走権を獲得しました。UTMBを知ってから、4年の歳月が経っていました。

(2022年UTMBのスタート時の様子、板谷さん撮影)
■4年の歳月を経てUTMBのスタートラインに立つ
2022年8月、私はUTMBの開催地であるシャモニーに向かいました。体を現地の気候に慣らすため、レース3日前に現地入りし調整を行いました。前日に受付と必携装備のチェックを受け、26日にいよいよレース当日を迎えました。緊張は少しありましたが、それ以上に気持ちは昂っていました。
UTMBの制限時間は46時間30分。コースは険しい山岳地帯です。胃腸を壊すランナーが多く脱水や低血糖をおこします。不眠で夜間も走るため幻覚を見るランナーも珍しくありません。
8月26日18時、いよいよレーススタートです。序盤のペースは速いです。第1関門の制限時間が厳しいのです。選手はここでふるいにかけられます。私は制限の2時間前に関門を通過し、次の山岳地帯に向かいました。時間帯は夜です。暗闇の中にヘッドランプの明かりが数珠繋ぎとなります。壮観です。
夜が明けるころ長い山岳地帯を抜け、イタリアの観光地、クールマイヨールに到着しました。私は預け荷物を受け取り、新しいウェアに着替え、行動食を補給しました。ここまでに選手たちは不眠不休で走りいくつもの峠を越えてきます。でもここはまだ中間地点。心折られてここでリタイヤする選手が多いのです。
この先の山岳地帯はフラットなセクションです。眼前に広がる巨石でつくられる岩山たちは圧巻でした。UTMB最大の山場、標高2530メートルのフェレ峠を越え、長い下りを降りきるとラ・フーリーに到着します。雰囲気から、この小さな村がスイスであるとわかりました。同時にすごく遠くまで来たなと思えました。

△眼前に広がる巨石でつくられる岩山に圧倒されながら走る板谷さん

△2022年UTMBで板谷さんが
使用したギアなど
--- 偽ピークとの戦い ---
マップで残りの山が3つであることを確認し、次のエイド、シャンペ湖に向かいました。シャンペ湖に向かう道は登り坂です。大した勾配ではありませんが、消耗が激しいためとても長く感じ、私は山を登っていると勘違いしました。山を登ったつもりの私はシャンペ湖について愕然としました。「ここからあと3つあるのー!?」私は辟易とした気分で妻に電話をかけ、ゴールまであと半日かかることを伝えました。 3つのうちの最初の山を超えトリエンに到着したころに日が暮れ、2回目の夜になりました。誰もいない真っ暗な山道を疲労困憊の体で延々と登ります。峠は風が強く、雨が降っていました。体が冷え込まないようにレインウェアを着込みました。厳しい時間帯でした。バローシンに到着した時、スタッフから「少し寝た方がいい」と言われました。疲労が顔に出ていたようです。でも休むことはしませんでした。ゴールまであと17キロ、そして次が最後の山。もうゴールすることしか頭になかったです。「ありがとう、でもすぐ出発する!」と伝え先に進みました。 巨大な山が眼前に現れました。モンテ峠です。UTMBの中でここが最も苦しい登りでした。山頂に見せかけて山頂ではない、「偽ピーク」が多いのです。山頂と思しきポイントまで登ると、そこは山頂ではなく遥か上の方にヘッドランプが見える。これを何度も繰り返すのです。10回は繰り返したと思います。そして本当の山頂に着きました。登りは終わったと思いました。しかし、眼前には細いアップダウンを繰り返しながら延々と登山道が続いています。私は冗談抜きで叫びました。「もうふざけんなー!」
--- 不眠不休の36時間35分 ---
最後の力を振り絞って登山道を進み、最後のエイド、ラ・フレジェールに到着しました。小さくて静かなエイドです。ゴールまではわずか7キロ。私はエイドのスタッフにお礼を言って足早に出発しました。後は下るだけです。でも足が痛くてほとんど歩くようなスピードで降りていきました。眼下にシャモニーの灯りが見えてきました。「ついに終わるんだ」と思いました。涙があふれました。これまでの道のりを思い出していました。UTMB目指した時から、1日も練習を休んだ日はありませんでした。雨の日も雪の日も走りました。体調が悪い時もルティーンを崩すのが怖くて、少しだけでも走りました。練習時間を確保するために、そして仕事や生活に悪い影響を出さないように色んなことを調整しました。大きな目標に臨むとき、単に練習だけに着目するのではなく、大げさに言えば自分の生活や人生をかける、そういうことなんだと思いました。
山を下りシャモニーに戻ってきました。街に入ってすぐに歩道橋を渡ります。本当の「The Last Climb」です。ゴールに近づいた時、私は妻に電話をかけ、今からゴールすることを伝えました。明け方なので街に人は少ないですが、それでも拍手を送ってくれました。
レースタイム36時間34分35秒。私はついにゴールしました。初めてUTMBを知ってから5年の歳月が経っていました。長い道のりでしたがUTMBは私にとってかけがえのない経験になりました。支えてくれた多くの人たちに心から感謝しています。これまで、私は私自身のために走っていました。でも今は違います。自分が頑張ることによって、それが誰かの力になればいいなと思っています。誰かを勇気づけるために、これからも挑戦を続けていきたいと思います。

△ゴールした時の板谷さん
■ところで何の仕事をしているんでしたっけ?
トレイルランニングと山岳救助を専門にしています。と言うのは冗談ですが、2023年10月から宮崎大学医学部看護学科の教授として勤務しています。専門分野は在宅看護で、研究はもちろん、学生向けに講義もしています。笑
講義は主に、在宅看護や社会福祉、それから統計学の科目を担当しています。学生の主体的な学びにつなげるため、グループワークや討論などのアクティブラーニングを積極的に行っています。私の授業で眠ることはできません!(笑) 特に在宅看護の授業では「感情を揺さぶる」ことを狙い、演劇や哲学カフェなどを取り入れています。かなり変わったコンテンツだと思います。演劇を取り入れた授業は看護教育学学会でベストプラクティスアワードを受賞したこともあります。看護師および保健師の国家試験対策にも力を入れており、学内では国家試験対策委員を努めています。また、自身のYouTubeチャンネルで国家試験対策動画を配信しており、全国の?学生が視聴しています。その他、就職活動支援、面接対策、小論文対策などなど、よろず相談所的な役割となっています。
主たる研究テーマは看取りです。日本では本人の望む場所で最期を迎えることが難しいのが現状です。これを少しでも改善するために、地域の専門職と一緒に様々な取り組みを行っています。その他には災害支援、地理情報システム、ビックデータの解析など手広いテーマで活動しています。最近はハノイ国家大学、JICAと連携しベトナムの低体重児に関する研究も行っています。私は宮崎に来てまだ間もないため、今は宮崎県でのフィールドを広げるために頑張っています。
 △講義中の板谷さん、よく見ると着ているのはUTMBのフィニッシャーズベスト
△講義中の板谷さん、よく見ると着ているのはUTMBのフィニッシャーズベスト
▼板谷さんが書いた論文
(1) Operational Management and Improvement Strategies of evacuation centers During the 2024 Noto Peninsula Earthquake ―A Case Study of Wajima City―
(2) Factors Associated with Behavioral and Weight Changes Across Adult to Elderly Age Groups During the COVID-19 Pandemic
(3) Using Spatial Scan Statistics and Geographic Information Systems to Detect Monthly Human Mobility Clusters and Analyze Cluster Area Characteristics
(4) 行政・地域データの横断的連結モデルによる多角的分析とEBPMへの活用 ~石川県羽咋市での健康増進分野を事例に~
(5) Childcare Center Evacuation to Vertical Shelters in a Nankai Trough Tsunami: Models to Predict and Mitigate Risk
■ 宮崎に来て初めて迎える元旦に起こった故郷の悲劇
--- 青島神社で初詣をしていたその時 ---
今年の1月、私の故郷である能登半島を地震が襲いました。その時、私は宮崎大学から車で15分くらいの場所にある青島神社で初詣をしていました。新年の始まりを祝っていたその瞬間、妻が「能登で地震だよ!」と知らせてくれました。急いで携帯を確認すると、「震度7」と表示されていて、「これは大変なことになった」と思いました。
震源地に近い輪島市に住む両親のことが心配で、すぐに電話をかけましたが、繋がりませんでした。幸いにも、一度だけLINEが繋がり、無事であることを確認できましたが、その後はすぐに連絡がつかなくなりました。青島からの帰り道、車載のテレビには「輪島市で火災が発生している」とのニュースが流れていました。映っていたのは私が幼少期に育った河井町でした。東日本大震災の時の火災を思い出し、不安が一層強まりました。案の定、火は燃え広がり、河井町の広範囲が焼けました。
その後、道路の損壊により能登にアクセスできないという報道が続き、私は何もできない無力感に苛まれました。しかし、1月4日の夜、石川の友人から道路が復旧したとの知らせがありました。翌日、私は石川に向かい、その友人の助けを借りて、渋滞を避け、真夜中に輪島に到着しました。

両親はすぐに逃げられるように1階のリビングで寝ていました。窓を叩いて起こした時、びっくりしていましたが、来てくれてありがとうと言ってくれました。家の中は倒れた家具でひどい状態でしたが、翌日、丸一日かけて片づけました。発災直後、父は家具の下敷きになったそうですが、幸いにも大きな怪我はありませんでした。 実家の片付けが一段落してから、私は知り合いのいる福祉避難所に向かいました。そこに集まった医師や看護師らと合流し、今後の支援活動について相談しました。その後、1週間現地に滞在し、医師らと一緒に能登の避難所を巡回し、避難者の健康観察等を行いました。道路の損壊や土砂崩れのため孤立した集落には徒歩で訪問しました。多くの避難所を回りました。ほとんどの避難所で電力は復旧していましたが、飲用以外の水が使えるところはほぼありませんでした。皆、お風呂に入れず手も洗えない状況でした。大変な状況の中、みな助け合って過ごしていました。公的機関がほとんど訪問できていない避難所でも、みんなで知恵を絞り、驚くほど適切に避難所が管理されていました。住民同士のつながり、忍耐強さ...これこそ能登の人間だと感じました。※写真:斜面崩落によって孤立した集落に医師らとともに向かう様子(2024年1月)
---故郷を離れてもできる復興支援---
宮崎に帰ってから、能登の状況をすぐに論文にまとめました。1月中に書き上げて投稿し、その論文はプレプリントとして公開されました。論文形式で発表された著作物としては最初のものだと思います。その論文は先日正式に受理され、現在掲載準備中です。
2月以降も月に数日程度能登に足を運んでおり、避難所の支援や研究者としての現地調査を行っています。住民のいなくなった孤立集落に残された猫に餌をあげるため、20キロの荷物を背負って片道10キロの山道を歩いたこともあります。この時ばかりはトレイルランで培った体力が役に立ちました(笑)。
6月末の報道によると、倒壊建物の公費解体は10パーセント程度にとどまっているようです。復旧には倒壊した家屋の撤去が必要ですが、その前には屋内にある必要な備品を外に出さなくてはなりません。そのためのボランティアが圧倒的に足りていないのだと思います。要因は様々ですが、ボランティアの受け入れ態勢が整っていなかったのでしょう。ただ、受け入れは随時拡大されているようですし、これから夏休みになります。多くのボランティアが能登を支援してくれることを期待しています。私自身もスケジュールを調整しながら、足を運ぼうと思っています。
災害は突然訪れ、私たちの生活を一変させることがあります。しかし、その中で人々が助け合い、支え合う姿に、社会の在り方を見たような気がします。能登地震は私にとって大きな経験となりました。これを次の何かにつなげていかなくてはいけないと今は考えています。
震災により亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、一日も早い復旧、復興を願います。
 △保健師チームと火災のあった輪島市河井町を調査(2024年3月)
△保健師チームと火災のあった輪島市河井町を調査(2024年3月)
■Mt.Fuji 100(2024年4月開催) で総合22位
--- トラブル続きのレース展開 ---
話しをトレランに戻します。これまで沢山のレースに出てきましたが、今回のレースはとくかくトラブルの多いレースでした。
スタート直前にザックのチャックが壊れポケットが一か所使えなくなり、中盤には時計が壊れて時間がわからなくなりました。一番焦ったのはソフトフラスク(水筒)の蓋が飛んでなくなってしまったことです。吸い口がないと水を保持できません。500ccのフラスクがもう1本あるのですが、「エイドを出るときには水1リットル以上持つこと」というルールがあります。考えた末、コース途中の道の駅でペットボトルを拾い、それを洗って代用しました。実際にレース中盤で装備品チェックがあったので、ペットボトルを拾っていなければ失格になっていました。
トラブル続きでしたが走り自体は悪くありませんでした。スタートしてしばらく、周囲に黒いゼッケンをつけた選手をちらほら見かけました。黒はエリートランナーであることを示すゼッケンです。序盤はゆっくり走るエリートランナーもいますから、周囲に黒ゼッケンがいるからといって、自分が上位にいるわけではありません。しかし、レースが進むうちに一人、また一人と黒ゼッケンの選手を抜いていきました。100キロ地点までに、トレラン雑誌に登場するような選手を何人も抜くことになりました。「もしかして自分、今日は調子いい?」と思いつつも、実際の順位はわかりませんし、粛々とレースを進めていました。
--- 両手・両足・顔面が痙攣、それでも故郷の想いを背負って前へ ---
122キロ地点の山中湖きららを抜けると、レースはここからが本番です。明神山への急な登りで、再び黒ビブランナーが現れました。そのゼッケンナンバーを見て衝撃を受けました。鬼塚智徳選手!!!彼は宮崎県民(清武近辺で練習しているらしい)で、前回のフジで3位の選手です。OSJ KOUMI 100 でも優勝しており、私は彼のファンでした。私は彼の前に出ました。もちろん彼は本調子ではないはずです。本調子ならここで追いつくわけがない。しかし、それでも!今自分がすごい走りをしていると確信しました。トップ争いには程遠いにしても「年代別入賞は狙えるかもしれない」と思いました。ここからは総力戦でした。レースは残り40キロ、できることはすべてやろうと思いました。
山中湖きららの先には、大きな山が3つ残っています。すでに120キロ以上走っており、疲労のため少しずつスピードが落ちてきました。それでも、必死で足を動かしました。二重曲がり峠、杓子山を抜けたところで日が暮れ、2回目の夜に入りました。山中湖きららから先は周囲に選手はおらず、ずっと一人で走っていました。最後の山、霜山に入りました。何度も登っている山で、普段ならあっという間に山頂に着きます。でも、この日はとても長く感じました。誰もいない山頂を抜け、下りに入りました。脚は疲労で痛いですが歯を食いしばって麓まで駆け降りました。あとはゴールまでロードと林道をつなぐ7キロです。エネルギーと水分が枯渇していました。両手、両足、顔面の筋肉が痙攣をおこしていました。それでも、必死で腕を振り続けました。疲労物質が全身を駆け巡り、心拍数が下がらず、呼吸も苦しくてたまりませんでした。心臓が止まるんじゃないかとすら思いました。でも、やめようとは思いませんでした。そこには、故郷の震災復興のためにも最後まで粘り抜くと、スタート前から決めていた自分との約束がありました。

△2024年Mt. FUJI100 最後の山、霜山の山頂付近
--- 死力を尽くした先に、年代別3位入賞の快挙 ---
ゴールの北麓公園に着いたときは、笑顔でフィニッシュする余裕はありませんでした。疲労困憊でのゴールでした。スタッフからはゴール後に年代別入賞のことは何も言われませんでした。あとからネットを確認しましたが特に情報はありませんでした。「入賞は逃したんだな」と思いました。でも悔いは何一つありませんでした。レースではすべてを出し切ったので。翌日に友達と焼き肉を食べているときでした。知り合いのランナーから「入賞している」とメッセージが届きました。総合22位、そして年代別3位入賞でした。


△2024年Mt. FUJI100に出走した際の装備品
■宮崎大学の近くの山にも沢山の魅力が
2024年のMt.FUJIではタイム・順位共に自己ベストを更新することができて楽しかったのですが、この感動を多くの宮崎県からのトレイルランナーと共有できたことが何よりも嬉しかったですね。いつもは、大会が終わったらすぐに自宅に戻ります。でも、今回はホテルで荷物を片付けた後、またゴール会場に戻りました。宮崎県からも、少なくとも12名が参加していました。私は宮崎県勢のみんなのゴールを待ち、喜びを分かち合いました。宮崎大学に着任して1年も経っていないのですが、既に沢山のトレイルランニング仲間がいます。
宮崎大学から車で5分程度の場所に、双石山(椿山)というNHKで放送されている「にっぽん百低山」でも紹介された山があります。標高は509mしかないのですが、森の中へ入ると、奇岩や巨岩がそびえ立ち、訪れる人を驚かせます。その山で、練習会が開催されていて、それに縁あって参加させてもらったことで沢山の仲間ができたんです。その仲間達の一部が2024年のMt.FUJI100に向けて、深夜0時にスタートして80kmを走破するトレーニングなどをしていて私も数回参加させてもらいました。
正直宮崎に来る前は、日本アルプスのような標高の高い山はないし、しっかりした練習ができるのか不安な部分はありましたが、こうして仲間もできて、仕事もプライベートも全力で取り組むことができています。
 △双石山で仲間と練習をする板谷さん(右から2番目)
△双石山で仲間と練習をする板谷さん(右から2番目)
▼にっぽん百低山「双石山(ぼろいしやま)・宮崎」吉田類といく【2023.4.24 NHK宮崎WEB】
https://www.nhk.jp/p/ts/NLKZP1Q6Y7/episode/te/QP33J7QKQ4/
■ 視線の先に
私には、もう一つクリアしたい山岳レースがあります。それは、2年に一度開催される「トランスジャパンアルプスレース(Trans Japan Alps Race、略称:TJAR)」です。
このレースは、日本海側の富山湾から日本アルプスの北アルプス・中央アルプス・南アルプスを縦断して太平洋側の駿河湾までの約415キロメートルを、8日間以内に、交通機関を一切使わずに自分の足で走るか歩いて走破しなければならず、一般の登山者であれば33日間かかる距離で、累積標高差は26,662mという、まさに日本で最も険しい山岳レースです。

2024年の大会参加のために応募して、厳しい参加資格審査は通過することができたのですが、残念ながら抽選漏れしてしまい、大会参加とはなりませんでした。この大会は2年に一度しか開催されないため、次に挑戦できるとしても2026年になります。正直、抽選に漏れてしまったことに少し残念な気持ちはありますが、UTMB(Ultra-Trail-Du-Mont Blanc)に申し込んだ際も2年連続で抽選漏れした上に、3年目は新型コロナウイルス感染症蔓延の影響で参加することができませんでした。 これまでもこのような感じだったので、私のトレイルランニング人生はこんなもんなんだと前向きに受け入れています。まさに人生と同じで上手くいくときもあれば、上手くいかないときもあります。どんな時も与えられた環境の中で全力を尽くしていくことが大切で、そうしていれば必ず2026年にチャンスが巡ってくると信じています。「2026年も抽選に漏れたらどうしますか?」。その時は2028年の大会に出れるようにトレーニングを継続するのみです。その時はもう52歳になっていますね。笑
※写真:2024年Mt.FUJI100ゴール後、復興チャリティシャツを着用して撮影
■ 取材を終えて
今回取材した板谷さんは、トレイルランニングを始めてわずか7年あまりで、数々の100マイルまたは100km級のレースを完走してきた。そして、30人しか参加資格を得ることができない日本一過酷な山岳レースに挑戦しようとしている。このようなレースは、当然命の危険にさらされることもある。なぜ、そこまでして過酷な状況に身を置こうとするのか。
板谷さんの専門分野は在宅看護。あるデータによれば、日本国民の6割から7割が自宅での死を望んでいることに対し、実際は8割以上の方が病院で最期を迎えている。この相反する状況を打破するためには、医療者側にも「みとり」に関する理解が必要とされることや、核家族化や一人暮らし世帯が増えている現状ではなかなか打開できない状況もあるが、「一人一人が元気なうちからどのように死ぬかを考えておく必要性がある」と、板谷さんは説く。
これまでに看護師として、保健師として、社会福祉士として、様々な立場で人間の老いや死と直面してきた経験があると考えられる。そして、そのような経験を積んできたからこそ、死と向き合い、今を大切に生きていこうとしている姿勢が生まれているのかもしれない。そして、2024年元旦に発生した故郷での震災が、これまで以上に今を大切に生きることを痛感させたのかもしれない。
それにしても、高校時代にボクシングでの県大会優勝経験、看護師としての勤務経験、アメリカ留学経験、スノーボードで全日本選手権出場を目指した経験、30代半ばでの大学編入学、日本百名山全頂制覇、UTMB完走、Mt.FUJI100での22位という偉業・・・・・。その時その時を全力で走り抜けた結果、既に2人分以上の人生を謳歌しているように感じた。
既に「アラフィフ」と呼ばれる年齢に達している。年齢はあくまで数字に過ぎないかもしれないが、2026年8月のTJARを見据えたトレーニングの道のりも険しくなるはずだ。そして、その困難を乗り越えて2026年のTJARのスタートラインに立つことができることを心より期待したい。その時も、北アルプスの山頂に到達すれば、次ははるか遠くに中央アルプスが見える。中央アルプスの山頂に到達すれば、次ははるか遠くに南アルプスが・・・。その道のりはまるで人生のように辛く苦しいことが多いはずだ。しかし、それを乗り越えた先に喜びがあり、次の山が見えてくることを板谷さんは知っている。
「明日死ぬつもりで、今日がんばる」。
常に死と向き合いながら、一度しかない人生を完全燃焼させ、自分自身をしっかり「みとる」という覚悟が随所に垣間見えた。
(後田剛史郎)
【関連情報】
▼宮崎大学医学部開講50周年記念特設サイト
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/50thanniversary/
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- 明日死ぬつもりで今日がんばる ~ 国内最高峰レースMt.FUJI100で総合22位に輝いたトレイルランナー教授 ~板谷 智也(いたたに ともや)さん