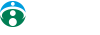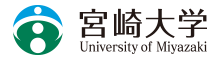世界初!生涯をとおして脳内でニューロンが作られ続ける 新規メカニズムを発見
2024年07月31日 掲載
世界初!生涯をとおして脳内でニューロンが作られ続ける新規メカニズムを発見
宮崎大学、九州大学などの研究グループは、生涯をとおして脳内でニューロンが作られ続ける新しいメカニズムを世界で初めて明らかにしました。この研究成果は、将来、認知障害やてんかん患者の病態改善に繋がる可能性があります。
この研究成果は、国際的な科学誌「EMBO reports」(2024年7月30日 オンライン公開)に掲載されました。
- 研究成果のポイント
- おとなの脳でのニューロンの誕生に重要なタンパク質(Derlin-1とStat5b)の発見
- 認知障害やてんかん発作にかかわるメカニズムの同定
- 認知障害やてんかん発作を改善させる化合物の発見
概要
記憶に重要な脳の海馬には、成体(おとな)になっても神経(ニューロン)を作り続ける幹細胞があります。この神経幹細胞は増殖しながら、その一部が新しいニューロンとなります。成体の脳の海馬で新しいニューロンが生涯をとおして作られ続けることを「成体ニューロン新生」といい、これは加齢とともに衰える脳の機能を維持するためにとても重要です。一方、認知障害やてんかん発作には、ニューロンの中の細胞小器官の一つ小胞体(注1)が関与することが示されていましたが、そのメカニズムは不明でした。そこで、脳内で小胞体の機能に重要なタンパク質Derlin-1(注2)を欠損したマウスモデルを作製し、解析しました。本研究では、Derlin-1が成体ニューロン新生を時空間的に制御していること、Derlin-1の機能が低下すると、認知障害やてんかん発作に繋がることを世界で初めて発見しました。さらに、ヒストン脱アセチル化酵素を抑制する化合物によって病態を改善させることにも成功しました。
これらの成果は、認知症やてんかん患者の病態を改善する創薬に繋がることが期待されます。本研究結果は、宮崎大学の村尾直哉助教、西頭英起教授、九州大学の中島欽一教授らによるもので、7月30日付けで、欧州分子生物学機構(EMBO)が発行する学術誌雑誌『EMBO reports』(エンボリポーツ)電子版に掲載されます。
(注1)小胞体:膜タンパク質や分泌タンパク質などを合成する細胞内の小器官(オルガネラ)の一つ。
(注2)Derlin-1:小胞体膜上に存在し、小胞体の品質管理に必須のタンパク質。
発表者名
村尾 直哉 (宮崎大学 医学部 機能生化学分野 助教)
松田 泰斗 (九州大学大学院医学研究院 統合的組織修復医学分野 講師)
門脇 寿枝 (宮崎大学 医学部 機能生化学分野 学部准教授)
松下 洋輔 (徳島大学 先端酵素学研究所 ゲノム制御学分野 助教)
谷本 幸介 (東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 ハイリスク感染症研究マネジメント学分野特任講師)
片桐 豊雅 (徳島大学 先端酵素学研究所 ゲノム制御学分野 教授)
中島 欽一 (九州大学大学院医学研究院 基盤幹細胞学分野 教授)
西頭 英起 (宮崎大学 医学部 機能生化学分野 教授)
添付資料
図1.本研究成果の概略図
発表雑誌
雑誌名:「EMBO reports」(2024年7月30日 オンライン公開)
論文タイトル:The Derlin-1-Stat5b axis maintains homeostasis of adult hippocampal neurogenesis
著者: Naoya Murao, Taito Matsuda, Hisae Kadowaki, Yosuke Matsushita, Kousuke Tanimoto, Toyomasa Katagiri, *Kinichi Nakashima, *Hideki Nishitoh( *:co-corresponding authors)
DOI番号:10.1038/s44319-024-00205-7
アブストラクトURL:https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44319-024-00205-7
その他詳細についてはこちらから
・プレスリリース 2024年7月30日
https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/20240730_01_press.pdf
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。