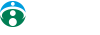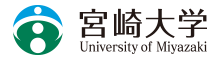関係機関とタッグを組み、宮崎の教育に貢献 ~ 愛情深く、子どもたちのロールモデルとなる教師を育てる ~戸ヶ﨑 泰子(とがさき やすこ)さん
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- 関係機関とタッグを組み、宮崎の教育に貢献 ~ 愛情深く、子どもたちのロールモデルとなる教師を育てる ~戸ヶ﨑 泰子(とがさき やすこ)さん

戸ヶ﨑 泰子(とがさき やすこ)さん
教育学部長 / 教授
神奈川県横浜市出身。
宮崎大学大学院教育学研究科教授。
研究分野は特別支援教育、臨床心理学。
早稲田大学大学院人間科学研究科修了。
2022-2023年度期日本認知・行動療法学会理事長。
2024年10月、宮崎大学教育学部長に就任。
宮崎大学教育学部の新学部長に戸ヶ﨑泰子教授が就任しました。戸ヶ﨑学部長はこれまで、特別支援教育や子どものメンタルヘルスの研究を進め、多くの論文を発表。多数の教育機関との連携も進めています。宮崎大学ができる地域貢献、これから取り組みたいこと、宮崎大学教育学部初となる女性の学部長就任の想いなどについてお話しいただきました。
■ なぜ、臨床心理学や特別支援教育の分野に進まれたのですか。
そもそものきっかけは中学時代にあります。学校が好き、先生のことも好き、友達もたくさんいました。けれど何かが違うという思いを抱えていました。同級生と話が合わないと感じることもあり、学校の先生とおしゃべりすることが多くなりました。職員室にいると時折、先生たちが職員同士の会話になることがあって、生徒に見せる姿だけでなく、生徒がいなくても先生の仕事は続いていくという様子を垣間見ることがありました。
その頃から、先生の仕事をお手伝いするような仕事ができるといいなと思い始め、進路を決定しました。子どものメンタルヘルスの問題や、子ども同士の人間関係づくりに関心があり、子どもの人間関係や親子関係に関することから研究をスタートしました。
■ 宮崎大学に来られたのは、どんなご縁からですか。
宮崎大学に行きたいと思った理由は、宮崎大学の先生です。私の研究テーマは、特別支援教育、子どもの対人関係、ソーシャルスキルなのですが、大学院進学を考えていた当時、子どものソーシャルスキルの研究を中核でされていたのが宮崎大学の先生方でした。佐藤正二先生、佐藤容子先生、高山巌先生です。大学院は先生方の下で学びたいと思っていましたが、当時、宮崎大学には大学院がありませんでした。所属している学会でご一緒している中で、宮崎大学の教員募集のことを聞き、先生方と一緒にお仕事ができると喜んで宮崎に来ました。宮崎大学には2004年に着任しました。当時は特別支援教育に関する制度改正の3年前で、着任してこれから宮崎の教育について知ろうという頃、すぐに宮崎県の特別支援教育のプランを策定するためのワーキング長を務めたことを思い出します。
■ 宮崎大学の役割について、どう考えられていますか。
首都圏にいると大学がたくさんあり、大学教員もたくさんいる。教育委員会の先生方もテーマに合わせて大学にアクセスします。でも宮崎の場合は、宮崎大学が知の拠点 として貢献できる大きなリソースとなっています。しっかりタッグを組んで二人三脚で宮崎の教育をどうするのか、それを軸に日本の教育をどうするのかということを一緒に考えていくパートナーとしての役割があります。存在が明確で顔の見える関係ができているというのは地方ならではで、お互いが理解できていると感じています。
リソースがないからダメということではなく、地方の緊密な関係の中で、しっかりビジョンを構築していると思います。大学に相談をもちかけても甲斐がない、そういう状況だと貢献できません。我々も最新の知見を蓄積し、必要に応じた情報提供ができるようにしていくことが重要です。それぞれが研究者としてのネットワークを持ち合わせているので、宮崎大学で対応できない場合は別の大学のより専門性の高い方と連携できる。窓口としての機能、つなぐ役割もあると考えています。

■ 教育に関する社会環境が変わっています。どのようなことを大切にしていますか。
世の中は共生社会、ダイバーシティ、そういった視点で共に手を取り合っていくという協働の考え方が大切になっています。学校ではそういった視点から授業をつくっていく、学級経営をしていく必要があります。子どもたちが成長し、そういう社会で生きていく、生き抜いていく力を育てていかなければなりません。コツコツと、小さな歩みに見えますが、ダイバーシティのマインドをもつ子どもたちが将来大人になったとき、共生社会の実現が一歩近づくものと期待しています。
■ 教育学部の新学部長に就任されます。どんなビジョンをお持ちですか。
少子化の時代、教育学部は他の学部以上に影響を受けます。その中で、子どもたちのより良い学び、多様な学びをサポートできるような専門性をどう学校の先生たちに提供できるのか。学校が学校だけにとどまらず、学校と地域の人が一緒になって子どもたちを育てていく。そういう地域をつくっていくという点では教育学部だけではなく、地域資源創成学部や、テクノロジーを活用しながら学びを深めるという場面であれば農学部、工学部との連携も必要です。連携によって、個別最適な学び、理解や学びの個人差に、もっと柔軟に対応していくことができると考えています。
いま、大学は厳しい条件の中で工夫しながらやっていく必要があります。ただ、大変なことに注目しているだけでは何も発展しませんし前に進みません。どんどん現状維持する方向になってしまいます。大学の先生方が前向きに新しいことをやってみようと思えるような環境になっていないと、学生が宮崎大学で楽しく学ぶことができないでしょう。私たちは学生にとってのロールモデルとしての役割を果たさないといけないと思います。そして、学生も教員を目指しているわけですから、何事にも児童、生徒、学生のロールモデルになっていくんだという姿勢で取り組んでいくことが大切です。楽しく仕事しようという気持ち、大変な中に楽しさ、よかったこと、達成感が味わえるような環境をつくっていきたいと思います。
■ 宮崎大学では女性初の学部長です。どんな想いがありますか。
ガラスの天井 という言葉がありますが、ちょうどそういう時期に生まれたのかなと思います。気負いはなく、できないものはできないし、できることは一所懸命にやる。それだけです。先述した佐藤先生たちと一緒に所属していた「日本認知・行動療法学会」でも理事長を務めました。設立50年で初の女性理事長でした。女性だからというわけではないと思いますが、皆さんからは学会を盛り立てるために気になることがあると、よくメールが届いていました。周りの方々にサポートをお願いしながら、より良い取り組みができればと思います。
■ 学生の皆さんに期待していることは?
大学も不透明な世の中を切り拓いていく時代です。大学生に対しても問題解決能力が求められています。社会の構造や仕組みが変わっていく中で、社会人になったときにどのように自分の力を発揮できるか。答えがない課題に自分なりに取り組むことが求められていく。これは小学生の頃からどうして?と自分なりに解決する、調べてみるという経験が重要になっています。

■ 教師を目指す方へのメッセージをお願いします。
直接指導している学生は、私のことを厳しい先生だなと感じていると思います。学生のことは応援していますし、かわいいです。けれどもその学生が将来出会う子どもたちのことを考えると、厳しくなってしまう。大切なことは時代が変わっても変わりません。その原理原則がしっかりしていると、教師として揺らがないでやっていけると思います。
巷では先生方の働き方が大変だというイメージが先行していると感じます。大変だという部分がクローズアップされていますが、やはり、教師は魅力的な仕事です。私たちは、学生の頑張ろうと思う気持ちを後押ししたいと思います。
人は誕生し幼児期を経て、小学校、中学校、高校、大学と学び、学んできたことが積みあがって20代、30代、成人・壮年期を迎え社会の中核的な役割を果たしていく。教師はそのための最初の基盤づくりという重要な仕事です。教育委員会の先生も学校現場の先生方も、魅力を感じながらいい仕事をされている。その姿を見てほしいと思います。
参考:
▼宮崎大学マガジン2024年10月号
https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/2024vol44.pdf
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- 関係機関とタッグを組み、宮崎の教育に貢献 ~ 愛情深く、子どもたちのロールモデルとなる教師を育てる ~戸ヶ﨑 泰子(とがさき やすこ)さん