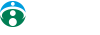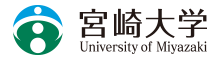血管が管をつくりながら枝を伸ばすしくみを解明 ―周りの硬さと血管内圧との力バランスの重要性―
2025年07月28日 掲載
血管が管をつくりながら枝を伸ばすしくみを解明
―周りの硬さと血管内圧との力バランスの重要性―
宮崎大学医学部機能制御学講座血管動態生化学の花田保之助教、西山功一教授を中心とした研究グループは、血管を新しくつくる血管新生*1において、血管基底膜*2による血管周囲の硬さと、血流によってもたらされる血管内圧*3との力バランス*4が、管腔構造をつくりながら血管の枝を伸長するために重要であることを発見しました。本研究は、著者らが熊本大学国際先端医学研究機構(IRCMS)所属時に開始し、宮崎大学への研究室移転後継続して行ったものです。本研究成果は、英国科学誌「Nature Communications」に、2025年7月28日(月)18時(日本時間)にオンライン版で掲載されました。
発表のポイント
- 血管新生では、管腔(血液が通るための管状の構造)がつくられながら血管の枝が伸びます。しかし、「血管の伸び」と「管腔をつくる」という異なる2つの現象が、どのように関係して血管新生が制御されているのかは不明でした。
- 本研究では、血管新生と、血流によってもたらされる血管内圧の両方を、微小流体デバイス*5上で再現する試験管内モデルのライブイメージング解析*6を独自に開発しました。この解析法を用いて、管腔形成後、血管内圧の上昇に伴って血管の拡張が起きると、血管内皮細胞*7の移動が減速・停止し、血管の伸びが遅れる現象を発見しました。
- しかし、正常な血管新生においては、血管周囲に適切に血管基底膜がつくられることで血管周囲が硬くなり、その結果、管腔形成に伴う血管の過剰な拡張が抑えられ、血管の伸びが滞りなく進むことも明らかになりました。さらに、マウス網膜血管新生モデル*8を用いた生体内解析と併せて、血管基底膜形成を介した「力バランス」の制御においては、ペリサイト(血管周囲細胞)*9が重要な役割を果たすことが明らかになりました。これによりペリサイトによる新たな新生血管制御機構が示されました。
- これらの結果は、血管を取り巻く力学的な環境が適切に構築されることで、血管の伸びと管腔構造の形成が統合され、両立できるようになるという、新たな血管を作るしくみを示すものです。本研究の成果は、臓器の発生・発達における力学的な環境の重要性を示唆し、がんなどの不適切な血管新生を背景とする疾患において、血管新生を標的とした新たな治療戦略の開発に貢献するものと期待されます。
論文情報
・論文タイトル
Biomechanical control of vascular morphogenesis by the surrounding stiffness
・雑誌名
Nature Communications
DOI: 10.1038/s41467-025-61804-z
・URL
https://www.nature.com/articles/s41467-025-61804-z
詳細はこちらから
https://www.miyazaki-u.ac.jp/public-relations/20250728_01_press.pdf
【補足説明】
*1血管新生
血管形成の過程には大きく2つの種類があり、脈管形成および血管新生と呼ばれる。脈管形成は、血管のない時期に新たな血管が形成される現象であるのに対して、血管新生は、既存の血管から新しい血管が出芽して伸長し、新たな血管網を形成する現象である。
*2血管基底膜
正常な血管のほとんどは、基底膜と呼ばれる薄い層状の構造で包まれている。血管基底膜は、おもに4型コラーゲン、ラミニン、ニドジェンなどのタンパク質によって構成される。
*3血管内圧
血管内を満たす血液により生じる水圧や、心臓のポンプ機能により血液が血管内に送り込まれることにより生じる血管内の圧力。
*4力バランス
血管は、血管内圧と血管の外側の圧力、血管壁にかかる張力がつり合うことで、管状のかたちが維持される。このつり合いを、ここでは力バランスと呼んでいる。血管内圧が上昇した場合、血管の外側が硬ければ、血管拡張が小さな程度でバランスの取れた状態になる。逆に血管の外側が軟らかいと、血管が大きく拡張してバランスの取れた状態になる。
*5微小流体デバイス
微小な流路を人工的に作成し、そのなかで液体や細胞を制御する技術。本研究では、独自に設計開発した流路内に、内皮細胞、肺線維芽細胞などの細胞と、フィブリン―コラーゲンゲル、培地を入れることで、血管新生を3次元的に再現する実験系を使用した。
*6ライブイメージング解析
顕微鏡を用いて細胞を生きた状態のまま連続的に撮影し、細胞の動きや組織の成長過程を追跡する実験解析方法。
*7血管内皮細胞
血管の内側(内腔)を一層で覆うように裏打ちする細胞。血管を構成する代表的な細胞である。
*8マウス網膜血管新生モデル
マウスの網膜は、出生直後から血管の形成が開始することが知られており、生体内での血管新生の評価モデルとして用いられる。
*9ペリサイト
内皮細胞によって構成される毛細血管に覆うように存在する細胞(図2A)。その被覆の程度は、臓器によって大きく異なることが知られている。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。