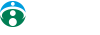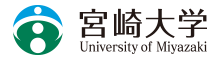いつまでも子どもの頃に抱いた夢を持ち続けたい 大澤 健司(おおさわ たけし)さん
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- いつまでも子どもの頃に抱いた夢を持ち続けたい 大澤 健司(おおさわ たけし)さん

大澤 健司(おおさわ たけし)さん
獣医師(農学部獣医学科教授)
1964年生まれ
1983-1989 酪農学園大学酪農学部獣医学科、獣医学研究科(獣医学修士号取得)
1989-1991 JICA海外協力隊獣医師隊員としてパラグアイに派遣
1992-1995 酪農学園大学大学院(4年次に休学)
1995-1997 JICAの海外長期研修員制度に合格.英国エディンバラ大学に留学(学術修士号 Master of Philosophy 取得)
1997-1998 酪農学園大学大学院復学・修了(博士号 [獣医学] 取得)
1998-2012岩手大学農学部獣医学科 助手、助教授(のち准教授)
2010年 グェルフ大学(オンタリオ獣医科大学) 客員教授
2012年から 宮崎大学農学部獣医学科 産業動物臨床繁殖学研究室 教授(現在に至る)
2022年から 世界牛病協会理事
2023年から 公益社団法人 日本繁殖生物学会理事長
趣味:旅行、コーヒー
座右の銘:為せば成る 為さねば成らぬ何ごとも
■ いつか自分も野生の王国に行ってみたい
幼い頃から恐竜や怪獣が好きでそれらに関わる仕事がしたいと思っていました。しかし、当然ですが恐竜は絶滅していますし、怪獣はフィクションの世界のもので、どちらも実在せず、それよりも生きている動物に関わりたいと思うようになりました。
特に影響を与えたのが、「野生の王国」というテレビ番組でした。1963年から1990年まで国内の地上波で放送されたドキュメンタリー番組で、小学生の頃はこの番組を見ることが毎週の楽しみでした。野生動物たちとその背景にある大自然の映像に心躍らされました。

■ 世界に羽ばたく小さな存在
何が私を今のような自分にしたのかはよくわかりません。しかし、小学生の頃から漠然と、とにかく海外に行きたいという強い想いがありました。
小学校の卒業文集の表紙は各自が自由に作ることになりました。その表紙に書いたタイトルは「世界に羽ばたく小さな存在」。どこからそのようなフレーズが出てきたのか不思議ですが、海外へのあこがれがあったのでしょう。
中学の時、新聞に広告を見つけました。広告サイズは全2段(15段で1ページ分)程度の小さなものでしたが、そこに記されていた「青年海外協力隊募集」というタイトルに目が釘付けになりました。「おっ!これは世界に飛び出せるチャンスなのでは!?」と。「いつか行けたらいいなぁ。しかし、俺に何の海外協力ができるのだろう?」という、胸が高鳴る想いと漠然とした不安を同時に持ったことは確かでした。
高校1年の終わりにバスケットボール部を退部後、帰宅部となって卒業後の進路を考えていた頃、たまたま母親が「友達の子ども(高校生)が将来獣医師になることを目指しているらしいよ」とふと漏らした一言が耳に残りました。「そうか、獣医学は面白そうだな。しかも、獣医師になれば海外協力ができるかも。協力隊員として『野生の王国』の世界に行くことができるかもしれない。」と考えるようになりました。この時に、希望する将来の進路、一つの目標が決まったと言えます。

■ 北の大地へ
高校卒業後は北海道の酪農学園大学に進学しました。ここから獣医師になるためのステップがスタートしました。
しかし、ステップアップどころか、大きなミスをしてしまうことに。大学2年の2月、酒に酔って地下鉄の線路に落ち、歩くことができなくなるほどの捻挫をしてしまいました(その時に電車が通らなかっただけラッキーです)。私が住んでいたのは古いアパートの2階で、もちろんエレベーターはありません。真冬だったために終日階段は凍り、健康な足でも慎重に下りないと滑ってしまう状態だったので、松葉杖の私は家から外に出ることができなくなりました。
時間を持て余したこの時に私は二つのことを覚えました。一つはタバコです。アパートの部屋で使っていた机は卒業した先輩から譲り受けたものでしたが、先輩は引き出しの中も片付けることなく僕にくれました。その引き出しにハイライトが1箱あったことを思い出し、それがきっかけで喫煙が習慣になってしまったのです。
捻挫がきっかけで覚えた習慣のもう一つは読書です。これは良い習慣となりました。その時に読んだ本の一つが司馬遼太郎の「竜馬がゆく」です。有名なタイトルなので読んだ人も多いと思いますが、幕末の激動の時代に新しい世の中を作ろうと全国各地を熱い志を持って東奔西走した坂本龍馬に心を大きく揺さぶられたことを覚えています。
足の捻挫がきっかけで、本を読む習慣が付いたことは、自分の人生を歩んでいく上でも非常に有意義だったと考えています。ちなみに、煙と付き合う生活は約12年でピリオドを打つことになりました。恩師から「国際人が喫煙しているのかね」と言われたことが決め手でした。

▲ 当時を振り返る大澤さん
■大学卒業 ~北の大地から南米パラグアイへ~
大学6年(1988年)の夏、入学時からの初志を貫徹して国際協力機構(JICA)青年海外協力隊の試験を受けて合格、翌年3月に卒業、獣医師国家試験も無事に合格し、その年(1989年)から獣医師隊員としてパラグアイに派遣されることになりました。
パラグアイではアスンシオン国立大学の分校に配属されました。その分校は首都から北に500 kmのコンセプシオンという地方都市に所在しており、ちょうど南回帰線が通る場所で、夏は40度を超える日々でした。配属先での私に対する主な要請は、現地で牛乳の生産増加に必要な品種改良を進めるための人工授精の普及、技術指導と、それに携わる人材の育成でした。現地の教員や学生に指導することになりましたが、日本で学んだ知識はあっても、技術移転のノウハウが十分にある訳ではなかったので、毎日手探りの状態でした。あるものを使って工夫をしながら自分が良いと思える方法を考えなければいけませんでしたが、今思うと課題解決力を育んだ時期でもありました。
また、大学を卒業したばかりの私が教えることができることはそれほど多くはありません。むしろ逆に沢山のことを教えてもらいました。語学力についても大学卒業時には全く話すことができなかったスペイン語も、無意識で喋るのが当たり前、いつまで話しても苦にならないくらいの状態になりました。スペイン語漬けのお蔭で、日本への帰国時には英語のドアやシューズという単語が思い出せない程でした。
パラグアイでは辛いことも楽しいことも沢山ありましたが、辛い経験は人生の糧になりました。地球の反対側の国での濃密な2年間はその後の私のキャリアの礎となっていると感じています。

▲青年海外協力隊時代の大澤さん(馬伝染性貧血の調査のため、任地の馬から採血しているところ)
■ 国際協力の専門家を目指す ~博士号取得を目指し大学院へ~
青年海外協力隊での経験で視野が広くなり、国際機関に勤務して世界各地の様々な課題を解決し、少しでも世界平和と人の役に立てる仕事をしたいという想いが強くなりました。
しかし、国際協力の専門家になるには、英語でコミュニケーションがとれることが必須となります。パラグアイでの2年間はスペイン語漬けの生活で、日本にいる時以上に英語を話す機会がなかったため、大学生の頃よりも英語力が落ちていました。当初は、パラグアイからの帰国後に、英語圏の大学院に留学しようと考えましたが、英語力もさることながら留学資金もなかったので、まずは母校の大学院博士課程に進学し、英語のブラッシュアップに励むことにしました。
パラグアイでの協力隊経験のなかで、自分に足りないものや専門的知識などが浮き彫りになったことから、大学院での生活は問題意識を高く持ちながら研究活動や自己研鑽を進めることができました。また、NHKラジオの「やさしいビジネス英会話」(実際は少しも"やさしく"ないレベル)で地道に勉強を続けました。大学院3年目には、JICAが実施する長期海外派遣研修制度における英語力の基準を上回るTOEICスコアに到達したこともあり、晴れてこの制度に合格、奨学金を得ながら自分が希望する大学に留学することが可能になりました。
留学先は熱帯獣医学センターを有する英国のエディンバラ大学に決めました。在籍していた大学院を休学して留学し、そこで獣医疫学の新たな研究手法を学び、英語力も高めることができました。エディンバラでの2年間も毎日が新鮮で、充実した2年間を過ごすことができました。帰国後は大学院に戻り、博士論文を提出して受理され、無事に獣医学の博士号を取得することができました。モノに恵まれなかった環境にあったパラグアイにおいて日々手探りで生きる力を磨いてきたことで、「どんなことでも強い思いさえあればどうにかなる」という信念を持てるようになりました。

▲イギリス留学時代の大澤さん(ロスリン研究所を訪問した際に、体細胞クローン羊のドリーと撮影)
■岩手大学から始まった教員生活
大学院修了後、岩手大学に助手(今で言うところの助教)として採用してもらえることになり、大学教員としての生活がスタートしました。その頃はまだ国際協力の世界に踏み出すことを考えていたのですが、大学教員としての業務(教育と研究や診療)に全力を尽くすうちに毎日が過ぎていきました。学生たちと共に実験をやり、そして農家の人々との交流を通じて、気が付いたら大学教員の世界にハマっていました。
岩手大学で勤務した14年間のうち、1年間をJICAの長期専門家として南米ウルグアイで、4週間をベトナムで過ごしました。これらの国際協力活動も大学教員だからこそ携わることができたといえます。
また、2010年3月からの半年間、サバティカル休暇(研究専念期間)を使ってカナダのオンタリオ獣医科大学(グェルフ大学獣医学部)で乳牛の子宮疾患に関する共同研究を実施する機会を得ました。そこで得たものは貴重な研究データだけではなく、多くの関係者との人脈、そして北米の大学の学位審査や獣医学教育や獣医療、さらに酪農現場の実際を目の当たりにできる、またとない体験でした。
ただ、この期間(私がカナダでの生活を始めて3週間後)に宮崎で口蹄疫のパンデミックが発生したことには心を痛めました。日本にいたら家畜の殺処分作業の応援部隊として岩手から宮崎に派遣されていたでしょうが、異国の地にいてはそれもできず、悶々として見守るしかありませんでした。また、当時は自分がその後、宮崎大学で勤務することになろうとは露にも思っていませんでしたので、人生とは不思議なものです。

△ 共同研究でお世話になった、Dr. Stephen LeBlanc (グェルフ大学獣医学部教授)と(2010年夏)
■ 岩手大学から宮崎大学へ
その後、縁あって2012年4月に宮崎大学に移ることになりました。
これまで、エジプト、バングラデシュ、ネパールなど、様々な国からの留学生を受け入れ、そして共に研究をしてきました。大学教員であれば海外に行かずとも留学生を受け入れたりすることで、日本にいながら人材育成という側面で国際貢献を行うことが可能であることにも気が付き、実感しました。
2014年にはアフガニスタンのカブール大学の教員を博士課程の大学院生として受け入れることになりました。これはJICAが主導する「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(通称PEACE)」の一環です。国際協力は私のライフワークでもあること、そして自分の礎を築いた協力隊や留学の機会を与えてくれたJICAへの恩返しという意味でも積極的に受け入れさせてもらいました。

▲JICA長期専門家として派遣されたウルグアイにて(郊外の牧場に車で出かけたが、牧場の途中で車を降り、
そこから先は馬しか通れない道ということで馬に乗って奥地に行き、そこで馬の去勢をすることになったそうだ)
■アフガニスタンで政権交代 ~ 帰国した元留学生からメールが ~
2021年8月、アフガニスタンから駐留アメリカ軍が撤退し、政権交代が起こりました。宮崎大学がPEACEプログラムで受け入れていたアフガニスタン人留学生の多くは、旧政権の政府系機関で働く大学教員や研究者等です。それ故に、新しい政権下では冷遇され、給与が削減されるなどして生活が苦しくなり、私が指導した元留学生からは「このままでは餓死してしまう。日本に退避することの手助けをして欲しい。」との一通のメールが私の元に届きました。
とはいえ、大学として受け入れる態勢が整っていたわけではなく、私もどうするべきか悩みました。しかし、仮にそこで「悪いけど何も手を差し伸べてやることはできない」と返信し、その後にその留学生や家族が命を落としてしまうことになったら私は一生後悔してしまうと思いました。宮崎大学農学部では、これまで40人以上のアフガニスタン人留学生をPEACEプログラムで受け入れてきたので、他の教員にも同じようなメールが届いているのではないかと思い、アフガニスタン人留学生を受け入れた教員に聞いたところ数人から返信がありました。その後、学部長の協力もあり、毎週一回関係者で集まり、具体的な支援策について意見交換をかわしながら段取りを整えていき、2022年4月以降に計7名の元留学生とその家族を宮崎に受け入れることが実現しました。
農学部長、そして学長や国際連携センター長など、大学が一体となっての支援体制が整ったからこそ可能となった支援であり、この場を借りて改めて関係の皆様方に感謝する次第です。
宮崎に来て13年目となりました。この地の基幹産業である畜産を通して地域を盛り上げること、そして産業動物の繁殖や獣医療を通して国際協力に関わることができる喜びと使命、そして国内外における未来の人材を育てていくという重要なミッションに携わることができることを誇りに思います。そして、これからも宮崎、日本、世界の畜産を支える人材の育成に貢献していきたいと考えています。
~ 取材を終えて ~
■7人のアフガニスタン人元留学生全員が宮崎県内の企業に就職
2023年3月28日、西都市役所で行われた記者会見で、大澤さんと関係者は笑顔に溢れていた。
3人の元留学生が西都市内にある企業に就職がきまり、7人全員の就職が決まったのだ。受入を開始して約2年。「7人とその家族が宮崎県内に移住できるまでの道のりは苦難の道のりでもありましたが、同じ熱い想いを持つ教員が農学部には沢山いたので乗り切ることができました」、「今回の支援については、私は当然のことをしただけと思っています」と、大澤さんは振り返る。
その言葉のとおり、大澤さんにとっては当然のことをしただけのことかもしれないが、しっかりとした信念を持ち、真に相手の立場にたって考えることができるからこそ行動に移すことができるのだろう。
前述のとおり、2022年4月から合計7名のアフガニスタン人元留学生とその家族を宮崎に受け入れることになったが、これだけの支援を行動に移すことができた大学は他にないだろう。大澤さんをはじめ、受け入れに尽力した農学部の関係者を誇らしく思う瞬間だった。

▲西都市で開催した記者会見にて(2023年3月28日)
■「世界に羽ばたく小さな存在」を創る
2024年11月に開催された宮崎大学農学部創立100周年記念式典には、大澤さんをはじめとする宮崎大学教員の指導を受けた元アフガニスタン人留学生の姿があった。彼らは皆、大学院修了後も宮崎県内で家族とともに暮らしていて、宮崎大学卒業生(修了生)としての誇りと愛着、そして宮崎大学への感謝があるからこそ、このような式典に参加するのであろう。
「世界に羽ばたく小さな存在」。大澤さんが小学6年生の時、卒業文集のタイトルに描いた言葉だ。現在は、大澤さん自身が海外に出て羽ばたく機会は減り、後身の育成がメインとなってきた。しかし、世界各国からの留学生を積極的に受け入れながら、日本人学生に対してもグローバルな環境の下で教育・研究活動を行うことで、日本人や外国人を問わず、一人でも多くの若者に「世界に羽ばたく小さな存在」となって欲しいという熱い想いを胸に秘めて日々の教育・研究に励んでいる。
2024年、宮崎大学農学部は100周年という大きな節目の年を迎えた。昨今は地球温暖化やCovid-19に代表されるような感染症の問題など、世界各国が協力して対応していかなければ解決できないことが多く、その中でも社会から農学部に期待される役割は高まっていると言える。そして、次世代を担う若者の育成は特に重要となってくる。大澤さんをはじめとする熱い想いを持った農学部教員が育成する「世界に羽ばたく小さな存在」は、次の100年をより良き社会にしていくだろう。 (後田剛史郎)

▲農学部創立100周年記念式典にて(2024年11月2日)
【関連情報】
▼宮崎大学・西都市・地域企業が連携した人道支援 ~ アフガニスタン人元留学生3名の就職先が決定 ~(2023.3.28)
https://www.miyazaki-u.ac.jp/newsrelease/international-info/-3-2.html
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは
Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
- トップページ
- 広報・教職員採用情報
- 広報
- 宮崎大学のひと
- いつまでも子どもの頃に抱いた夢を持ち続けたい 大澤 健司(おおさわ たけし)さん